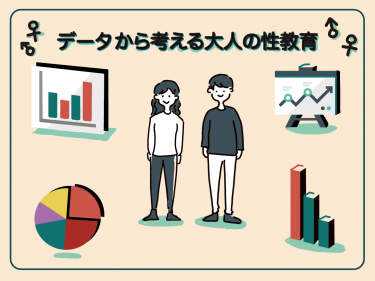毎月訪れる、恐怖の1、2週間。普段は怒らないようなことで、突然逆上されたりする、あの期間。
そう、パートナーの生理。毎回気をつかっているつもりでも、うまくいかず失敗したり、ヒヤヒヤしている人も多いのでは。
そんな男性陣に、生理前から生理中までの女性にどう接すればいいのか、僕なりのTIPSを共有します。少しでも参考にしていただいて、パートナーとの関係性の向上に役立てていただければ幸いです。
まずは生理などについて勉強する
もともと生理については全くといっていいほど無知だった僕。
ただ、今のパートナーが普段から生理についてオープンに話してくれたり、パートナーが読んでいたシオリーヌさんの『CHOICE 自分で選びとるための「性」の知識』という本を読んだことをきっかけに、生理への理解が深まった。
子宮の大きさが鶏の卵くらいのサイズであることや、PMSの意味を理解していなかったのはもちろん、PMDDなんて言葉は聞いたことすらなかった。
生理について勉強したことで、自分では体感できなくても生理に関する基本的な知識は頭に落とし込むことができ、寄り添い方の選択肢が広がった。
その一連の流れの中で、パートナーから教えてもらった精子セルフチェックキット「Seem」を実際に自分が使用してみたことも相まって当事者意識が生まれ、性に関することへの感心が高まったことも大きい。
今でも女性の体については分からないことは多いが、生理前後のパートナーへの対応は明らかに変わったと思う。
月によってPMSや生理痛の重さも変化することに留意する

以前から漠然と、女性は生理前や生理中はお腹が空きやすくなったり、ちょっとしたことでもイライラしてしまうという認識はあった。
しかし、彼女の生理にしっかりと向き合うようになってから、PMSや生理の症状には毎月違いがあることに気づいた。
月によっては空腹感やイライラの症状が全くないこともあれば、生理痛がいつにも増して重いこともある。
風邪にも色々な症状があるように、生理に関する体調不良や、PMSの症状などにも違いがあることを理解して接するようにしている。
生理は人によって違うため、ヒアリングをしっかりする
今振り返ると、これまでお付き合いしてきた人たちの生理前後の症状は全て異なるものだったということに気づいた。
とにかくがっつり何かを食べないと気が済まない人、甘い飲み物をずっと飲んでいたいという人、話しかけるだけで睨まれたりする人もいた。
男性であれば、自分の親から生理のことについて詳しく聞く機会はほとんどないと思うので、女性の友人やパートナーとやりとりをしていく中で、どのように接していくべきなのか意識する必要がある。
極端かもしれないが、生理のつらさを考えると、僕ら男性は自分が医者になったつもりでパートナーの生理の症状をヒアリングして、何をして欲しいのかを素直に聞いてみるのがいいと思う。
PMSや生理の時期を把握する

現在お付き合いしているパートナーからは、排卵期予測アプリ「Clue」のClue Connectという機能で生理周期を共有してもらっている。
パートナーに直接聞きづらいと感じている人もいると思うので、アプリで常に確認ができるようにしておくと、デートプランを決める際や、家事の分担を変更する際など、前もって計画を立てられるのでおすすめだ。
会社では女性社員にも配慮する(これからの課題)
これは僕も気をつけないといけないことなのだが、恋人や近い友人であれば生理による体調不良などについて配慮ができるが、いざ職場にいくと仕事が優先となり、生理による体調不良の人がいるかもしれないという思考がなくなってしまう。
生理中であることを会社の人に知らせる必要はないと思うし、男性社員も体調不良の女性社員に対して生理かどうかを聞く必要はないと個人的には思う。
ただ、人対人のコミュニケーションとして体調が優れない人がいたときに、サポートをするのは当たり前だし、ちょっとした気遣いがあるだけでも関係性は大きく変わると思う。
コミュニケーションなしに信頼関係は生まれない
月の中で1週間腹痛が続き、それが毎月あると考えただけで、僕は耐えられる自信はない。ただ、自分の体調が悪い時に、「大丈夫?何か欲しいものある?」と声をかけてもらえただけで、気持ちが落ち着くこともある。
大切なパートナーであるからこそ、相手のことを思いやり、相手目線で物事を考えられる「寄り添い力」が必要だ。男性が生理を理解するためにはとにかくコミュニケーション。
これは仕事でも言えることで、社内や社外でもコミュニケーションのないところに信頼関係は生まれない。
生理前後で相手が何を求めていて、どう接すればいいのかを普段から聞くようにしてみると良いのではないでしょうか。





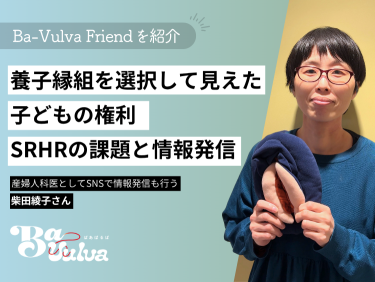
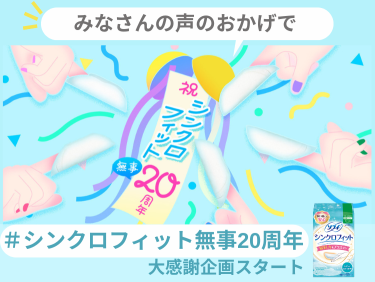

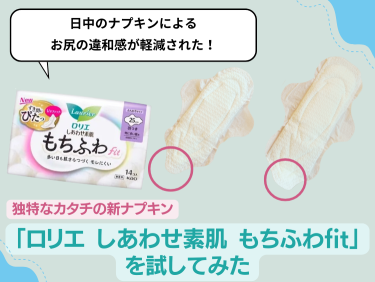



![YES インティメイト・ウォーターローション WB[さっぱり保湿ケア]](/assets/media/2022/02/1721113748052-375x375.jpeg)