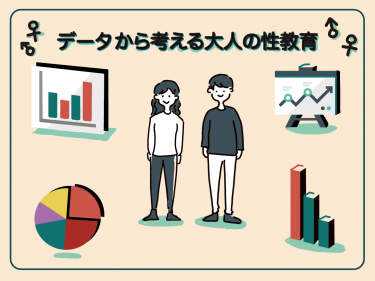こんにちは。uni’que若宮です。
全5回に渡ってお送りしてきた、『「ちがい」を活かすチームマネジメント術』も今回が最終回。読者のみなさんの「若宮ロス」が懸念されますが(されないw)、気を確かに持って最終回まいりましょう!
「正しさ」や「正解」を超えていこう。
これまでの連載では、
第1回は、「生理」と男女の「ちがい」を知る話
第3回は、「傾聴」すること難しさ
第4回は、「男のプライド」が邪魔する偏見について
上記について書いてきました。連載を通じてお伝えしたかったことは、人はそれぞれに「ちがい」をもっていて、視点もそれぞれに偏っている(=客観的な視点などない)、ということ。このちがいや偏りが文字通り「偏見」にもつながれば、すれ違いや相手の否定の原因にもなってしまいます。
「正義」の対義語は「別の正義」
という言葉があります。
たとえばジェンダーギャップの話で、「女性平等に取り組むことは正義である」という主張がされることがあります。
僕自身もジェンダーギャップは解消されるべきだと思いますし、「差別」とは闘っていくべきです。
また、当事者の人のこれまでの苦しみを思えば、「悪⇔正義」という強い言葉を使いたくなるのも無理はありません。
しかし僕はそれでも、「絶対的正義」や「絶対悪」は無い、とも思うのです。絶対悪に見える「殺人」ですら、戦時下や正当防衛のためには許容されることもあります。
しかし「正義」という言葉を使うとき、人は「そうではない人」を「悪」として客観的な事実のように決めつけてしまいがちです。
人はすべて「偏見」を持っている
完全に客観的な視点を持てる人はいませんし、人は自分のパースペクティブ(視点)からしかものを見ることができません。
つまり、人はなんらかの「偏見」を持っているのですが、「偏見」や「差別」と闘っているときには自分を「正義の闘志」だと感じ、「自分には偏見がない」と信じてしまうことがあります。
たとえば先日、マイケル・サンデル氏の著書を読んだのですが、そこには一見すると公平に思える「能力主義」の考え方ですら、いかに偏見と差別を生んでいるか、ということが書かれています。
参考:頑張りと自己責任が生む偏見 〜「能力主義」の分断を越えるためにはどうすればよいのか
たとえば「優秀な女性がもっと活躍すべき」というとき、この主張は「正しい」のですが、「優秀な」という言葉の背後で「学歴主義」による差別を生んでいることもよくあるのです。
大企業で働いていた頃、初対面で「どこの大学出てるの?」と聞き、その学校(を自分の出身校と比較して)によって態度を変える人がいました。
これは一見性別とはちがって根拠のある「区別」で「実力主義」や「能力主義」的には「正しい」ことのように思えます。
しかし下記の投稿からわかるように、大学進学率は出身地でも大きく異なります。つまり能力や実力そのものではなく、性別のように「たまたま」の生まれによって生じる格差でもあるのです。
こう言うと、「ほれみろ。女性活躍だけをいうのはおかしいし、むしろ差別だ」という議論のすり替えをされてしまうこともあるのですが、これを理由にジェンダーギャップを主張してはいけない、というのは間違っています。
実際、女性の進学率の地域差は下にみるようにさらにひどいのです。問題は、そっちだって差別してるだろ、ではなく、どちらの格差も是正していくことです。
注意したいのは、「自分には偏見がない」と思ってしまうと別の偏見が見えなくなり、差別してしまう可能性もあることを自覚し、「正義」や「正しさ」で語らない、ということです。
「正しさ」を伝える瞬間、人は脳内で相手を「正されるべき側」にしてしまいます。すると自分が偏っているということを自覚できなくなってしまうのです。
たとえば僕自身、子どもに「こっちが正しい」というような物言いをしてしまうことがあります。 しかし後で振り返ってみると、「子どもらしさ」の偏見を押し付けていたり、世代間の価値観のちがいを配慮できていなかった、ということも多くあります。
そしてより大事なのは、ジェンダーギャップの問題やあらゆる格差の問題は「女性 vs 男性」のように対立構造になったり、片側だけが解決に向けて頑張るものではなく、男女双方で協力して解決していく課題として、その“真ん中”に置かれるべきということではないでしょうか?
「幸せの形」もいろいろあっていい

万人にとっての「正義」はありません。そして、人はみんな偏見を持っています。
だからこそ話し合うことが必要です。
これはチームマネジメントにおいても重要なことです。
「正しい」から「こうすべき」ではなく、自分たちが一緒に目指す価値や目標は、メンバーそれぞれの価値観を共有した上で自分たちで考えてつくるものなのです。
企業では独自のCore Values(行動指針)を定めているところも増えています。企業の活動においてもこれが「正しい」という1つの解や「絶対善」というのはありません。自分たちのチームがどんな価値を目指すのか、それはそれぞれのチームごとに異なるのです。
ロシアの文豪、レフ・トルストイは次のように書きました。
「幸福な家庭はどれも似たものだが、不幸な家庭はいずれもそれぞれに不幸なものである」
しかし、これからの時代、「幸福な家庭」もまた「それぞれ」似ていないものになってもいいのではないのでしょうか。
男性が働かねばならない。女性は家事をしなければならない。子どもは親のいいつけに従わなければならない。
そんな「べき論」がありますが、社会通念は変わっていきます。一般論に振り回されず、それぞれの幸福の形をみつけてもいいはずです。
そして「正しさ」や「べき論」を超えて自分たちで話し合うことで、メンバーそれぞれの意見や視点を取り入れ、チームとして焦点を合わせる効果があります。
[今月のやってみよう]
パートナーや家族との中に「Our Rules」はありますか?
もしなければぜひ話し合ってみましょう。「Our」というのには2つの意味があります。ひとつは一般論や「べき論」ではないこと、もうひとつは昭和の「家訓」のように家父長だけが決めず、みんなでつくるものだということです。
[STEP1] それぞれが大事にしたい価値観、許せないことを書き出す
理想だけでなく、ポジティブ、ネガティブの両方を出し合いましょう。こんなことを大事にしたい、こうされると嫌、それぞれ付箋などに書き出します。言葉にするより個人ワークで書き出した方が出しやすいでしょう。
[STEP2] 「わたしたち」だけのルールをつくる
出てきた意見をもとに「わたしたちのためのルール」をみんなで考えましょう。シンプルな方がいいですがきれいごとになってしまうので無理にかっこよくする必要はありません。また、一般論と違っても気にせず「わたしたち」だけのルールをつくりましょう。ポイントは多数決せず時間がかかってもじっくり議論してみんなが納得することです。
[STEP3] ときどき見直す
一度つくったルールもずっとそれがいいとは限りません。時間が経ちそれぞれが歳をとるなど変化があったら見直しましょう。年に1回ずつくらい見直す機会があるといいかもしれません。
『「ちがい」を活かすチームマネジメント術』では、お互いの「ちがい」を押し付けたり押しつぶしたりせず、それぞれの「ちがい」を活かすことを考えてきました。
個の「ちがい」を大事にするということは、その集合体であるチームもそれぞれ「ちがい」をもつチームになるということです。
自粛警察をはじめ、今の日本は少し息苦しくなっているところもあります。「正しさ」や「正義」はそれに当てはまらない人を敵視し、相手への共感を失わせ、攻撃的な心境にしてしまいます。
だからこそdiversityやinclusionが必要です。
いろいろな価値観があることを受け入れ、共存しようとすること。しかしそれは、「みんなちがってみんないい」と安易に言ってしまうことでもありません。
そうではなく、異なる価値観をお互いに共有し、ときにはぶつかり議論しながらその葛藤の中でOur Rulesをつくり、都度見直していくことこそが「ダイバーシティ」なのではないでしょうか。
この連載を通じて、家庭やチームでそうした価値観の見直しの機会を持っていただけたらとてもうれしいです。




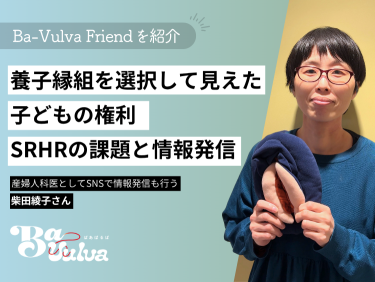
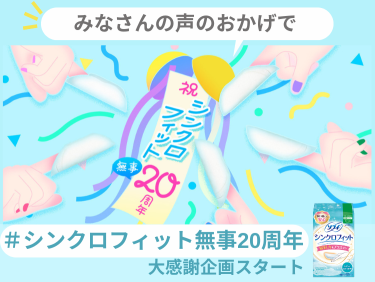

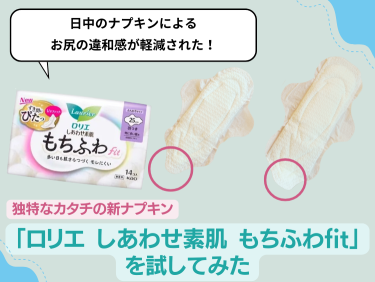



![YES インティメイト・ウォーターローション WB[さっぱり保湿ケア]](/assets/media/2022/02/1721113748052-375x375.jpeg)