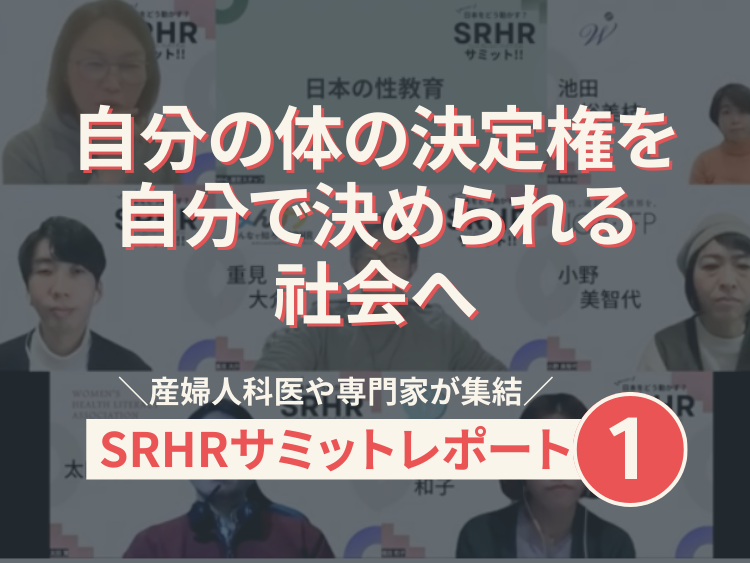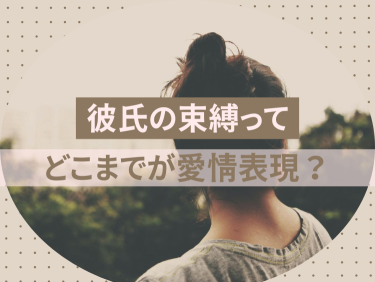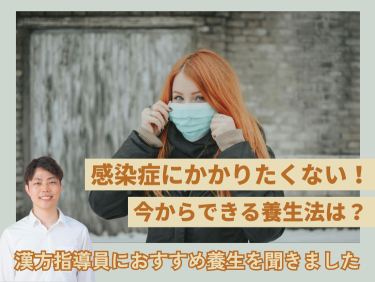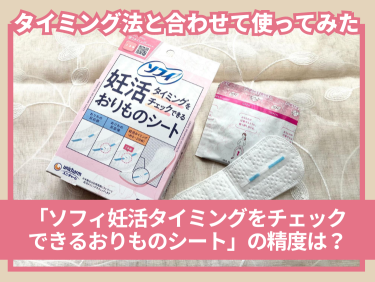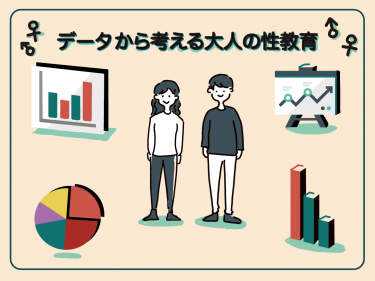2月末に開催された「ウィメンズヘルスリテラシー協会」と「みんリプ」主催のオンラインイベント「変わらない日本をどう動かす? SRHRサミット2023」。
SRHRの分野に精通する産婦人科や専門家が集結し、SRHRの歴史を紐解きながら現状の課題とこれからを語り合いました。当日のレポートを3回に分けてお届けします。

日本語で「性と生殖に関する健康と権利」と訳される「SRHR(Sexual Reproductive Health and Rights)」は、すべての人の「性」と「生き方」に関わる重要なこと。私たち一人ひとりが適切な知識と自己決定権を持ち、自分の意思で必要なヘルスケアを受けることができ、みずからの尊厳と健康を守れることを意味します。
アフターピル(緊急避妊薬)の市販化が足踏み状態になっていたり、母体保護法の規定で中絶の際にはパートナーの同意書が必要だったり、自分の体とその後の人生を決める重要な選択であるのにも関わらず、国や文化、慣習などが妨げとなり、自らの意思で決められない現状があります。
本イベントでは、「SRHRの歴史」、「SRHRの概念」、「男性におけるSRHR」の3つのセッションと、SRHRにまつわる分野を議題としたトークセッションが行われ、参加者と一緒にSRHRの未来を考える時間となりました。
SRHRの歴史を振り返る
イベントをファシリテートするのは、ウィメンズヘルスリテラシー協会の代表を務める丸の内の森レディースクリニック院長の宋美玄先生。
産婦人科医として、専門的な視点から妊娠・出産、セックス、セクシャルウェルネスなどの女性の体の悩みに関する発信を行なっています。
まずは、国際協力NGO「JOICFP(ジョイセフ)」の小野美智代さんによる、「SRHRの歴史をひもとく」をテーマに、SRHRの歴史や概念を振り返るセミナーからはじまりました。
日本の家族計画
日本におけるリプロダクティブ・ヘルスについて小野さんは「今は少子化対策が最重要課題として優先的に取り組まれている日本ですが、国際的に見ると女性と赤ちゃんが亡くならない国として、いち早くリプロダクティブ・ヘルスを成功させた国でもあります」と話します。
戦後の復興期間に人工妊娠中絶の件数が増加し、1952〜1955年までの期間に妊産婦死亡率が増加。
この状況を解決するために、 政府は日本家族計画協会(JFPA)と協力し、「家族計画プログラム」を1952年に開始しました。望んでいない妊娠が存在するのであれば、「妊娠する前に家族計画をしよう」と呼びかけました。
医療機関と行政が連携し、出産までのリスクをできる限り回避する体制が整えられています。
リプロダクティブ・ヘルス/ライツの概念が登場したのは1994年。それまでの間に、日本では人口増加の抑制と遺伝的に疾患を持っていると判断された人々の出生を抑制することを目的とした「優生保護法」が、1970年代に実質上の中絶を禁止とする方針に改定されます。この優生保護法は、1996年に「母体保護法」として一部改定されました。

リプロダクティブ・ヘルス/ライツが登場するまでの国際的な流れ
次に、国際的な流れを追っていきます。2022年の11月に、世界の人口は80億人を超えました。これは、2018年の予測値より約2年早く到達。先進国では人口が減っているものの、世界規模で見るとまだまだ増えている状況です。
食糧不足や環境破壊など、人口増加による脅威は1950年あたりから国際的に問題視され、人口問題について話し合う国際会議が開かれるようになります。中国で行われていた「一人っ子政策(1979年〜2014年)」のように、国の政策としてトップダウンで人口増加を抑制する動きもありました。
リプロダクティブ・ヘルス/ライツの概念が誕生したのは、1994年にカイロで開かれた国連主催の国際人口開発会議(ICPD)。
これまでの国際会議でも、女性の権利やジェンダーが議題に上がっており、1993年にウィーンで開催された世界人権会議では、「セクシュアルヘルス」や「セクシュアルライツ」についても話されています。
しかし、カイロの国際人口開発会議では、さまざまな文化や宗教、政治的な背景のある179カ国の国が集まっているため、『セクシュアル』という言葉が入ることによって行動計画の採択が取れないという問題がありました。そこで「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」として、明文化されたという背景があります。
このカイロの国際人口開発会議では、人権やジェンダーの課題にフォーカスされ、人口問題をマクロからミクロの視点に転換し、ひとりひとり個人の問題として捉えられるように変化した、重要な会議だったようです。

2000年以降のSRHRの動き
2000年に定められた「SDGs」の前身となる、ミレニアム開発目標「MDGs」では8つの目標がまとめられました。
ゴール1:極度の貧困と飢餓の撲滅
ゴール2:初等教育の完全普及の達成
ゴール3:ジェンダー平等推進と女性の地位向上
ゴール4:乳幼児死亡率の削減
ゴール5:妊産婦の健康の改善
ゴール6:HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止
ゴール7:環境の持続可能性確保
ゴール8:開発のためのグローバルなパートナーシップの推進
とくにこのゴールのなかでもリプロダクティブ・ヘルス/ライツに関わるゴール5の到達が難しく、専門家の意見をもとにターゲットと指標が以下のように変更されます。
目標・ターゲット
2015年までに妊産婦の死亡率を1990年の水準の4分の1に削減する
↓
2015年までにリプロダクティブ・ヘルスへの普遍的アクセスを実現する
指標
・妊産婦死亡率
・医師・助産婦の立ち合いによる出産の割合
↓
・避妊具普及率
・青年期女子による出産率
・産前ケアの機会
・家族計画の必要性が満たされていない割合
このターゲットと指標の変更により、妊産婦死亡の削減、避妊実行や医師の立ち合いによる出産の増加といった成果をあげました。
一方で医療従事者の少ない地域、とくにサハラ以南のアフリカで妊産婦死亡率が高く、地域の格差が顕著となったようです。
2015年には、MDGsが積み残した課題を引き継いだ持続可能な開発目標として「SDGs」が策定されます。
小野さんは、日本と世界における、SDGsの捉え方の違いについて次のように言及しました。
「日本では17のカラフルな目標として目にすることも多いと思いますが、世界では『People(人間)』『Prosperity(繁栄・豊かさ)』、『Planet(地球)』、『Peace(平和)』、『Pertnership(パートナーシップ)』の5つのPで成り立っていると考えられています。とくに『People』に関わる1〜6を達成できれば、すべての目標の達成率を加速させるだろうと言われているんです」
それを裏付けるように、リプロダクティブ・ヘルス/ライツに関わる家族計画(ファミリープランニング)の普及がSDGsの達成にもっとも効果的であると記載された論文が2016年時点で発表されています。
また、カイロの国際人口開発会議から25年後の2019年には、アフリカのケニアで人口開発会議が開催され、SRHRに残されたとくに深刻な課題として3つのゼロが提唱されました。
・家族計画サービスへのアクセスが満たされない状況(アンセットニーズ)をゼロに
・予防可能な妊娠・出産による妊産婦の死亡をゼロに
・児童婚などの有害な慣習とジェンダーに基づく暴力をゼロに
最後に、「新型コロナ感染症や、世界各国で起こっている紛争、災害など、人道危機下において、女性のSRHRをめぐる現状が厳しさを増しています」と、今、世界で起こっている出来事との関連と、急を要するSRHRの現在地が伝えられました。
ー
SRHRサミットレポート全3回の続きは、以下からご覧ください
第2回 SRHRの概念と男性にとってのSRHRとは?SRHRサミットレポート 2/3
第3回 SRHRを日本に根付かせるための課題とは?性教育・性的同意年齢・アフターピルと妊娠中絶薬 SRHRサミットレポート 3/3