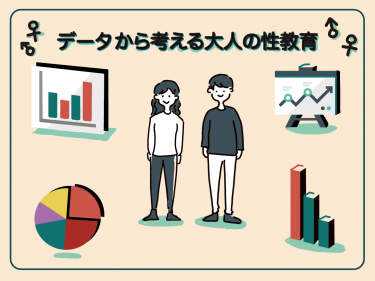100年以上前に、まちの小さな文房具店として開業した株式会社オカモトヤ。
今では事務用品であるペン1本から、OA機器、オフィス家具、オフィスの内装に至るまで、働きやすい職場環境を提供する商社へと成長した。これまでオフィス用品を通して、さまざまな企業の働き方を見つめてきた老舗だ。

2022年7月、オカモトヤの4代目社長に就任したのが鈴木美樹子さん。
鈴木さんは、自身が経験した不妊治療や妊娠・出産を経て、性差による働きにくさの解消を目指した新規事業「Fellne(フェルネ)」を立ち上げた。
フェルネでは女性のための防災備蓄キット「災害用レディースキット」や、企業向けフェムケアアイテムのECサービス「Fellne Store」などを展開している。
「職場での女性活躍推進の輪を広げ、より良い社会にしたい」と話す鈴木社長に話を聞いた(インタビューは2022年12月に実施)。
不妊治療を経験して直面した健康課題
ーー フェルネはどのような経緯で立ち上げたのでしょうか?
鈴木社長(以下、同):ある管理職の男性が「親の介護が心配です」と話していて、実際に介護離職した男性もいました。「妻が介護疲れで倒れてしまい、妻のケアをしたいので会社を辞めます」と。
私は社員の働きやすい環境をつくることを中心に、オカモトヤの一社員として、10年ほど従事してきました。それは、労働環境が変わってきていることを目の当たりにした10年でした。
その中で出産や育児、介護について社内でも話題にあがるようになりました。
これからは少子化の影響で労働人口が減っていきますし、働く人が減れば当然、文具を使う人も減っていきます。なんとか社会に貢献できるような新しい事業ができないか。それが、当社にゆかりのあるビジネスであればなお良いと考えたんです。
そこで2022年、私が社長に就任したタイミングで働く女性をサポートする新規事業フェルネを立ち上げました。

ーー 女性に着目したきっかけはあるのでしょうか?
私は38歳のときに、不妊治療を経て出産を経験しました。
36歳で結婚し、パートナーと話し合って妊活を始めたときに初めて、不妊治療のクリニックで医師に「左の卵管が詰まってます。このままでは着床しないですよ」と言われました。「卵管って詰まるの?」と驚きました。生理は毎月きていたし、これまで婦人科系に何か問題があるとは思っていなかったので。
その後、不妊治療を経てなんとか子どもを授かり、育休から仕事に復帰したときふと思ったんです。独身の女性社員たちは皆、自分の体のことを知っているのかな?と。
卵巣が年齢とともに劣化して、卵子の数も減っていく。生理がきていても子どもを授かれるとは限らない。人それぞれの生き方、考え方は多様ですが、もしも将来的に子どもを授かりたいと思っているならば、体に関する知識は持っておいたほうがいいのではないかと思いました。
ーー ご自身の不妊治療経験があったからなんですね。
私が経験したことを、みんなに伝えるのは、それはそれでちょっと押し付けがましいのではないか…とも思いましたが、自分と同じような問題に直面する人はきっといるはずです。
働く女性が増えて、会社がこういう問題にも踏み込むべき時代になったのではないかと感じています。
生理の悩みを話し合って生まれた「災害用レディースキット」
ーー 近年はさまざまな企業が健康経営に力を入れていて、中でも生理や不妊治療、更年期など女性向けの課題に取り組む企業も増えてきていますね。取引先の企業から要望が寄せられることもありますか?
ひとつ例をあげますと、2021年に大手メーカーから「女性向け防災用品」のご相談をいただきました。工場に勤務する女性従業員のために災害時に使えるような生理用品やフェムケア商品をセットにして常備したいというご要望でした。
東京都は災害時に備えた3日分の備蓄を義務化していて、通常の防災用品なら用意している企業が多いですが、女性の場合それだけでは不十分です。なので通常の防災用品に、女性にとって必要なものをプラスできたらと。
こうした需要があるとわかり、まずは「災害用レディースキット」をフェルネのサービスとして展開しています。

ーー キットの中身は女性向けのサニタリー用品が充実していますね。
生理用ナプキン、シンクロフィットなどの使い捨てタイプの生理用品や夜用ショーツ。経血漏れが不安になる場合もあるので、黒いズボンも入っています。入浴もできない災害時を想定して、デリケートゾーン用の拭き取りシートや膣洗浄アイテムもセットしました。
災害時に生理になったとしても、とりあえずこれで3日間は過ごせるような中身を揃えています。

ーー 生理に関する需要は当事者でないとわからないので、企業側にとってもありがたいセットですね。
女性メンバーで話し合って中身を決めたので、そうだと嬉しいですね。弊社はオフィス用品の商社なので、働く環境で何か困っていることはないか?と社内でよく話題にします。
そんな中で私は「タンポンを使っても漏れるときがあるんだけどみんなはどう?」「捨てるときどうしてる?手が汚れるし、あの小さいサニタリーボックスに捨てるのが嫌なんだよね」と自分の生理の困りごとを話題にしました。
今まで仕事中に何度も経血が漏れて嫌な思いをしていることや、お腹や腰が痛くても鎮痛剤を飲んでやり過ごしてきたこと。リアルな悩みを話をしていくと、他の女性社員からもさまざまな声が上がりました。
生理に悩む働く女性たちに対して何かできないかと考えて防災キットを作ったり、「サニタリーボックスちっちゃくない?」という話からストレスなく快適に使えるトイレのあり方を考えて商品化しました。
人生100年時代、これからのトイレのあり方とは?
ーー 鈴木社長自ら赤裸々に話すことで会話が生まれ、需要が可視化されたんですね。そこまで踏み込めていない企業も多いと思います。
生理に関してはネットにもたくさん情報が上がっていますけど、実際に働く環境においてはまだまだ不十分だと感じます。男性社会が根強い企業だと、女性の健康課題に触れることをタブー視していたり、女性側も話すことが憚られてしまう。
ですがオフィスも制度も、個人の健康の重要性も時代とともに変わってきています。
ーー オフィスに関しては、具体的にどんな需要の変化があると思いますか。
政府は人生100年時代を掲げていますが、今後社員が70歳まで働くことになった場合、個人の健康のセルフメンテナンスが必要になると思うんです。例えばトイレに関しては、個室でやらないといけないことが増えてきます。
男性でも尿もれパッドを使っていたり、糖尿病の疾患があればインシュリン注射を自ら打たなければならなかったり、ご高齢の方に限らず人工肛門をつけている方もいらっしゃいます。

弊社が提供している「オールジェンダートイレ」は、性別にかかわらず働く人のさまざまな体の健康問題に寄り添うことを目的として開発しました。
今(2022年12月)は在宅勤務をメインとしている企業も、コロナが明けて従業員がオフィスに戻ってくる。より価値のあるオフィスづくりをしていかないといけないと思います。
男性の管理職でも、女性の健康問題を考えるきっかけに
ーー 「Fellne STORE(フェルネストア)」についても教えてください。
フェルネの一環として、加入いただいた企業向けに情報サイト「Fellne STORE(フェルネストア)」を提供しています。

月経カップや吸水ショーツなどのフェムケア商品が購入できるECサイトです。個人で買うこともできますが、企業は福利厚生として導入することで従業員をサポートすることもできます。
企業の方に知って欲しい女性の健康課題にまつわるコラムも読めるようになっています。私がミレーナを入れたときの体験談もコラムに綴って紹介しています。
ーー どのような狙いがあるのでしょう?
生理や更年期に関しては、自分から取りに行けば情報は豊富ですが、興味がなければ知らないことが多いですよね。
管理職の男性が急に生理について踏み込むのは、伝え方によってはセクハラだと言われかねない状況もあると思うんです。だからこそ、なかなか取り組めていない企業も実際に多いです。
そこで、女性活躍を推進していきたい企業はこちらをどうぞ、と言えるものを用意したかった。男性の管理職が我々の提案を持ち帰って「こういうものを提案されたんだけど、需要がありますか」と女性社員に話を切り出すきっかけにしやすいと思います。
女性活躍推進を広げていくことが事業の根幹なので、今後は研修メニューや、卵子凍結サービスなど、さらに充実させていきたいです。
性差による働きにくさを払拭する、大きな一歩へ
ーー 御社は「FemAction®(フェムアクション)」を掲げていますが、どんな思いがありますか。
女性活躍推進やフェムテックなど、女性のQOL向上につながる取組みの総称としてFemAction ®を掲げました。商標登録を申請中です(2022年7月現在は商標登録済み)。これは独占する目的ではなく、いろんな企業でみんなに使ってほしいので、他の企業の縛りをなくすために申請することにしました。
女性活躍推進法は2022年4月に改正されて、義務化が対象となる企業が中小企業にも広がりました。また育児・介護休業法の改正にともない出生時育児休業(産後パパ育休・男性版産休)制度も導入され、今まさに企業にとっては変革のときだと思います。

私自身も感じたように、性差による働きにくさがまだまだ残っているなか、どこからなら企業が取り組みやすいのか?私たちオフィス用品の商社ができることは何か?を常に考えています。
生理や更年期に関して話すことがいいのではなく「話ができる空気感がある」ことが会社としては大事だと思います。
ーー 鈴木社長は、今後フェムアクションを広げてどんな社会にしたいと思いますか。
女性が働きやすい環境は、だいたいみんなが働きやすい環境なんじゃないかなと個人的には思っているんです。これまでさまざまな制度が男性目線で作られてきました。ですが、女性の働きやすさを意識した本当の働き方改革が必要だと思います。そうしていかないと日本は豊かにはならない。
私の9歳と7歳の二人の娘が大きくなったときに「性別に関係なく、働けるし稼げる。そのすべはたくさんあるよ」と自信を持って伝えられる社会になって欲しい。未来を生きる子どもたちのためにも、フェムアクションを広げていきたいと思っています。
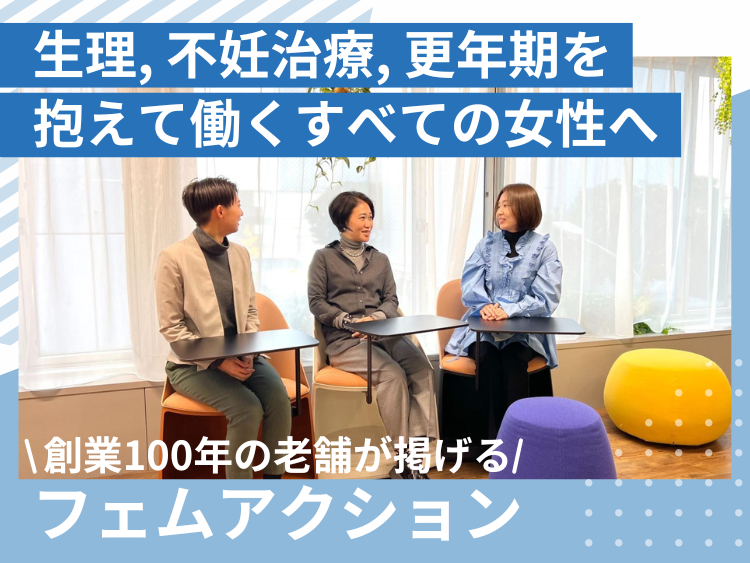

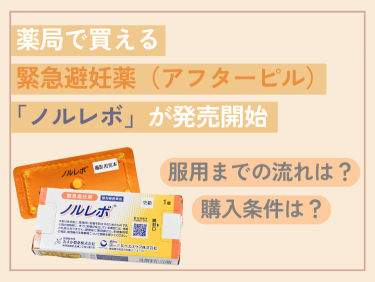





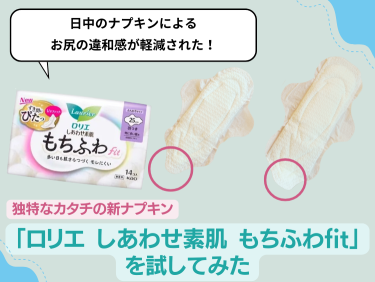



![YES インティメイト・ウォーターローション WB[さっぱり保湿ケア]](/assets/media/2022/02/1721113748052-375x375.jpeg)