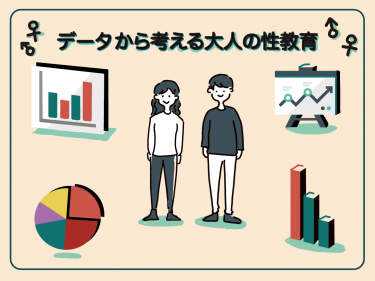小5の冬、例年通りインフルエンザが流行した。もれなく感染したぼくはあの日、自室のベッドで熱にうなされていた。
専業主婦の母がたまたま買い物に出掛けていて、家にひとりきりだったのをよく覚えている。尿意を覚えて布団から這い出た。そしてトイレに入って下着を降ろすと、クロッチにべったりと茶色い何かが付着していた。
熱いはずの体から、急速に体温が奪われていくのを感じる。保健体育ではまだきちんと習っていなかったが、ぼくはすでに本で知っていた。初潮だ。ついに来てしまった。
「死にたい」、とすぐに思った。どうして、なんで。もし来るとしても、あと数年は先だと思っていたのに。そもそもぼくに、月経なんて必要ないのに。だってぼくは、「女の子」じゃない。
家族やクラスの子たちに、絶対に知られたくない
物心ついたときから性別違和を自覚していたぼくは「月経」の存在を知ってからというもの、来たる日に怯えていた。男の子になりたいんじゃない、でもぼくは確実に女の子じゃない。
将来は「大人の女性」になんかならないし、乳房もふさわしくないし、たとえ子宮だとか卵巣だとかがあったとしても子どもを産む機能なんか搭載されてていいはずない。そんなの、間違ってる。
誰にも言わなかったけれど、そしてどうにも自分を「女の子」と思えぬことが”変”だとわかっていたけれど、そう強く確信していた。
まもなく帰宅した母がぼくを捜す声で、我に返った。ぼくがトイレにいることを知った母が、扉の向こうから腹の具合でも悪いのかと訊ねてくる。どう答えたらいいかわからずしばらく押し黙っていたが、永遠にそうしているわけにもいかない。汚れた下着を握りしめたまま、ぼくはのそのそとトイレから出た。
「ああ、来たんやな」と母は言い、ナプキンの収納場所と使い方を教えてくれた。とくべつ驚いたりはしていなかったように思う。ぼくの知る限りクラスではまだ1人しか初潮が来ていなかった。
そういう情報さえも子のプライバシーなど微塵も考えずシェアしてしまう「保護者たち」の無神経さと残忍さのせいで、クラスの女子全員が「〇〇ちゃんにはもうセーリが来てる」と知っていたのだ。
体が自分を裏切って「大人の女性」になろうとしている
母もまた例外ではないことをよく理解していたから、「絶対に誰にも言わないで」と固く口止めした。「パパにも、弟にも、絶対に内緒にして」。誇張でなく生命が懸かった懇願だったが、母は他者の感情の機微に無頓着なひとだった。

インフルエンザが治った数週間後の保護者会の翌日、クラスのリーダー格の女子に「ちーちゃんってもうセーリなんでしょ」とトイレ内で詰め寄られたのだ。違うと嘘をついて個室に逃げると、古い扉の隙間からその子が覗いているのに気付いた。心臓は縮み上がり、ひゅうっと気管が狭まった。
隙間から覗くあの卑しい目が、今もぼくは忘れられない。
知っていたのはクラスの女子だけじゃなかった。あとからわかったことだが、母はぼくの懇願を無視して(赤飯を炊きこそしなかったが)父にも伝えていた。知っている人間の数が多いほど、本当のことみたいになっていく。
単純な恥ずかしさよりもなによりも、自分のものであるはずのこの体が自分を裏切って「大人の女性」になる準備を始めたという事実と、身と心が引き裂かれている子の苦しみをちっとも察せない母の裏切りが、ぼくを打ちのめした。
見た目の「女性性」への拒絶感
ここまで書いて、苦笑する。もう20年も前の出来事を、まるで昨日のことのように思い出せる自分に。それほど自らの身体を強く強く嫌悪していたのだろう。怨恨の念は幸福な思い出よりはるかに強烈だ。
31歳になったぼくは、自らのジェンダー・アイデンティティを既存のカテゴリで表すならば「ノンバイナリー」がいちばん適切だと認識している。そして月経のあるこの身体を、あいかわらず疎んでいる。
ただ忌避感は、胸オペ──乳房縮小術を受けたことによって幾分か軽くなった。あのころよりももっと具体的に身体への違和感を言語化できる今、あらためて説明してみたい。ぼくは性器の形状や内臓よりも、「可視化される女性性」を強く拒絶していた。
だからある日突きつけられた下着についた血液に、狼狽し、絶望したのだ。それゆえ大人になってからも内摘(子宮と卵巣を摘出すること)はせず、胸オペのみ受ける選択をした。
見た目で「女性」と判断されるものが排除されれば、ぼくの場合は概ね満足だった。だって、服を着てたら性器の形なんて他人にはわかんないし。もしも明日の朝にょきりとペニスが生えてきたとしても、それはそれで「まあいっか」と過ごしていく気がする。翻って、今の形状──ヴァギナにも、「まあいっか」くらいの感覚で生きている。
月経の有無で性別が決まるわけじゃない
自分の性別違和への解像度が高まった今、「月経」というものについて改めて考えてみたい。そもそも初潮は「女性予備軍」のひとにだけ来るものじゃないにも関わらず、アラサー世代のぼくたちは学校で「身体が大人の女性へ成長する準備」だの「子を産む母体に変化した証拠」だのと教わった。
もし、そうじゃなかったら。「初潮」は単に「月経のあるひと」に来るものであり、子を孕む機能が発育し始めたために起こる現象で、だけど月経があるからといって必ず妊娠しなきゃいけないわけでも妊娠するわけでもないのだと、シンプルにそう教えてもらえていたら。もしかしたらあの日の幼いぼくの傷つきは、もう少しマシになっていたかもしれない。
月経の有無で性別が決まるわけではないこと。そもそも「女性」の身体にはさまざまなかたちがあること。──「女性以外の人間」で月経があるひともいること。それを学んだ今は、毎月の血祭りをうんざりしながらもやり過ごすことができている。ピルやPMS・PMDD対策サプリの力を借りながら。
女性でも男性でもないひとは、世の中にいっぱいいる

初潮が来て、絶望していたあの日のぼくへ。まずは、生きていてくれてありがとう。絶望しながらもなお、最悪の選択をせずにいてくれたことが嬉しい。
そしてあなたは月経があろうとも、「女性」じゃない。月経があることと、「女性」ではないことは、矛盾しない。あなたが覚える自認と身体との剥離、自らを「女性ではない」と感じることは、”変”なんかじゃない。女性でなくても、男性でなくても、おかしくない。
この世に性別は2種類しかないと未だ多くのひとが勘違いしているけれど、本当はそんなことないし、あなたのように感じるひとは実のところたくさんいる。まだあなたが知らないだけで。
どうかあなたのその「女の子じゃないけど、男の子にもなりたくない」アイデンティティに誇りを持ち続けてくれ。その先に現在の「女性じゃないけど男性でもない」ぼくが、呼吸してマックを食べてキーボードを打っている。ぼくは──ぼくたちは、確実にこの社会に存在し、生きているのだ。












![YES インティメイト・ウォーターローション WB[さっぱり保湿ケア]](/assets/media/2022/02/1721113748052-375x375.jpeg)