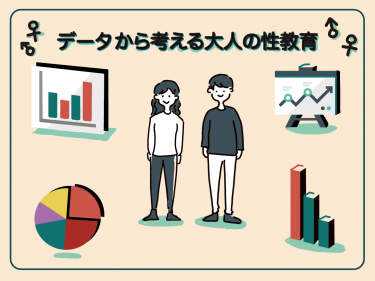“わたしは女の人をみるたびに、かならずその人がどれくらい不幸かどうかを想像してみる癖がある。”
川上未映子の短編集『愛の夢とか』の中の一節だ。
「そうそう、わかる!」と、この本の読書会で話したものの、その場にはあいにく同じ感想を持った人がいなかった。まるで私が他人の不幸を期待する卑劣な人間のように思われなかったか、あとからちょっとだけ心配になった。
私は決して目の前の女性に「たくさん不幸であってほしい」と望んでいるのではいない。相手のたくさんの不幸を想像して精神的にマウントを取ってやりたいとは全く思わない。厳密にいえば量は大して重要ではなく、「どれくらい」より「どんな」の方がはるかに重要なのだ。
それぞれの「不幸」で通じ合った、ある美容師の女性
数年前、着物を着る必要があり、着付けと髪のセットのために初めての美容室を訪れた。担当してくれた40代くらいの女性美容師さんが、どんな話の流れだったか、髪のセットの途中で自身の仕事について話し始めた。
「昔はね、タレントさんについてモルディブの撮影なんかにも同行してたんですよ」
なにげない思い出話のようだが、彼女の「昔はね」を聞いた瞬間、私はビビッときた。この感覚をうまく言葉にすることはとても難しい。
彼女が少しだけ寂しそうに笑ったからか、あるいは伏し目がちだったからか、「昔はね」を聞いた途端に、彼女の「昔」から「今」に至るまでには、とても一筋縄にはいかない、しかし彼女の信念に基づいた熱いドラマが潜んでいるな、と直感的に確信した。
だけどもちろん大人なので、無作法に踏み入ることはしない。代わりに私は自分のことを話した。
「そういえば私もモルディブに行ったことがありますよ。昔、結婚してて。そのときは今と違って、たまたまお金がたくさんあったので」
するとその瞬間、鏡越しに美容師さんとばちっと目が合った。彼女は私を見ながらにやっと笑って「面白い人生歩んでますね?」と言ったのだ。
和装用の髪のセットは思いのほかあっという間に終わったので、彼女とそれ以上の話をすることはなかったけれど、私は今でもあの美容師さんのことをよく思い出す。
あの一瞬、私はたしかに彼女のままならない人生、彼女だけの不幸を想像した。次の私のターンでは、彼女もきっと同じように私を見た。その結果、私たちは確かに通じ合った。心の中でガッチリと手を握り合い、互いを「おもしれー女!」と称え合った。
枠から外に出た者への羨望と、それに魅了される自分

「幸せな家族はどれもみな同じようにみえるが、不幸な家族にはそれぞれの不幸の形がある」
『アンナ・カレーニナ』の初っ端からトルストイさんがこう言っているように、幸せに比べて不幸にははるかに豊かなバリエーションがある。
なぜなら多くの人にとって「幸せ」とは予測し得ることしか起きない状態が続くことであって、その枠内に収まりきらなかったものがおおむね不幸に分類されるからだ。
選択すれば茨の道であるとわかっていても、その人が避けて通らずにはいられなかったもの。誰が見ても茨の道であることは明確なのに、その人にだけは栄光への道、天国への階段に見えていたもの。
あるいは本人を含む誰も予測し得なかった、運命のいたずら。人がそういうものに翻弄されて直面する状態を不幸と呼ぶなら、私は人の不幸の中にこそ、その人固有の形があるに違いないと思う。
学校、職場、家庭——私たちの身の回りには大抵いつも理想とされる形が用意されていて、いじらしい私たちはつい無自覚に自分をそこに合わせようとする。フィットしない自分を見つけると、いったい何が悪いのかと自分を顧みたり、責めたり、思い悩んだりもする。
けれど、そもそも理想とされる既存の形は決して私のためのオートクチュールではなく、元はと言えば世の中がスムーズに回る一助となるような、何らかの目的をもって誰かが決めたものだ。それが全て、すっかり自分に合って、すっかり居心地が良いなんてはずがない。
その結果、窮屈さに耐えきれず不登校になったり、休職や退職をしたり、離婚をしたりするかもしれない。ともすれば、それは挫折や敗北、逃亡のようにみなされ、一般的な「幸せ」の状態とは対極にあることかのように扱われたりする。
たしかに、当人にとってみても既存の枠からはみ出るというのは大変なことだ。一度は道なき道に放り出され、地図もない中で広大な世界から、次の目的地を自分で見つけ出さなければならない。そんな苦労を背負い込むなんて、やっぱり不幸じゃないかと思う人もいるかもしれない。
でもその人は、そうしてまで、自分だけの形を守ろうとしているのだ。たとえ多少の苦労を背負ってでも、どうしようもない自分を殺さずに、辛抱強く向き合っている人なのだ。そういう人は、既存の規格にすっかり収まりきって、安心している人よりはるかにタフだし、なにより圧倒的に面白い。
逆に、自分が「幸せ」の枠の中にいると考えている人の中には、ときに「不幸」をウイルスか何かのように思っている節があって、「運のいい人のそばにいると運気がアップする」の延長線で、暗黙のうちに不幸とみなした人を、自分から遠ざけようとする。
別に放っておいてもなんら問題ないだろうに、近くにいると、わざわざ仲間内で議題にしてまで悪しきことと確かめ合ったりもする。そのあまりの忌避っぷりが、なにか臭う。そうでもしなければ不幸の強い誘惑に負けてしまいそうになるんじゃないか。枠から外に出た者への羨望や、不幸に魅了される自分への恐れがあるのではないだろうか。
仮にそうだとすると、「幸せ」もなかなか奥深い。幸せな状態とは常に幸せを失う危険と隣り合わせであるから、現状を守る努力を続けなければならない。
けれども幸せだからといって常に満ち足りているとも限らない。だからふとした隙間に悪しき不幸の誘惑が入り込まないように注意して、外の世界に目を向けないように努めるのだ。目に入ったら問答無用で否定する必要がある。
「幸せ」という小さな牢獄と、「不幸」という無限の荒れ地……。
なんだか右に行くも地獄、左に行くも地獄みたいな、身も蓋もない話になってしまったけれど、振り返ると数年前に初めて離婚を考えたとき、たしかにこの2つが、私の目の前に鎮座していた。
どこまでも広がる荒地を前に

当時、私は専業主婦だった。いろいろあって当時の夫は乱心しており、それまで潤沢にあったはずの資産が消え、数カ月にわたり生活費は振り込まれなくなっていた。話をしようとするも逃亡を続け、一向に話にならない夫。
それでも、このまま結婚を続けていた方がいいんじゃないか。そうすれば形だけでも「幸せ」の枠の中に留まっていられるのではないか。根拠のない現状維持路線と、いや、尊重し合えないパートナーとはきっぱり決別!という新章スタート路線。
この結論を出すまでには、数年の時間が必要だったけれど、最終的には後者を選んだ。
どうせそれなりにお金をもらって離婚したんだろうと思われているかもしれないが、実際のところ、当時うちにはお金がなかったので、全くそんなことはなかった。
現在は物書きという不安定極まりない仕事に就いていることもあって、一生懸命働いているけれど、正直、老後にはかなりの不安がある。輪をかけて「ロスジェネ世代の単身女性の50%は老後に過度な貧困状態に陥る」という新聞記事を読み、当事者として恐々としている。
ただそれでもひとつだけ言えることは、少なくとも私は今、私の選んだ、私だけの地獄を生きているということだ。
ここには私しかいないから、誰かを妬ましく思うこともない。振り落とされないように必死にしがみつく必要もない。ときにはどこまでも広がる荒地を前に、一体どこに行くべきかと呆然と立ちすくむこともあるけれど、行こうと決めたらどこにでも行ける。
ただし、どこに行っても孤独が後をついてくるのがちょっと厄介だ。これに気を取られすぎると、自分だけの地獄に誰かを引き摺り込みたくなる。でも、それは多分よくないことだろうと思うから、孤独とはなんとかうまくやっていく方法を見つけなくてはならない。
だから、同じようなやり方で生きている誰かに出会うと、不思議とすぐにわかる。目の前のその人の完全オリジナルな不幸に思いを馳せる。
「面白いじゃん、やるね!」って、お互いの地獄から手を伸ばしてガッチリ交わす心の握手は、それまで携えてた孤独なんて一瞬で吹き飛ばしてしまうほど、疑いようもない人間の温かさを伝えてくれるのだ。

ランドリーボックスでは、特集「#わたしたちの離婚」をはじめました。
「おめでとう」という言葉をもらって結婚した日。
「お疲れさま」という言葉を自分に投げかけて離婚した日。
どちらも私の人生の選択で、どちらも私の人生の通過点でしかない。
私が私らしく生きるため、貴方も貴方らしく生きるため、それぞれが決めた選択を労いたい。
ランドリーボックスでは、新たな一歩を踏み出したそれぞれの「離婚」をテーマに、個々人の生き方について考える特集「#わたしたちの離婚」を開始します。












![YES インティメイト・ウォーターローション WB[さっぱり保湿ケア]](/assets/media/2022/02/1721113748052-375x375.jpeg)