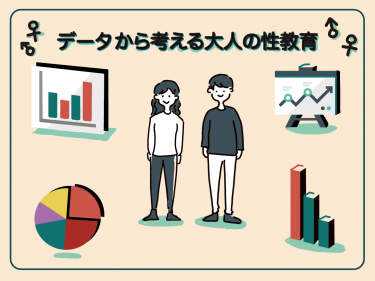SNSやニュースで見かける「ルッキズム」「ミソジニー」「エイジズム」。聞いたことはあるけど、実はよくわかっていない──そんな人も多いのではないでしょうか。
「痩せて可愛くなったね」「女が家事や育児を優先するのは当たり前」「その年齢でその服着るの?」
これらの言葉は特定の属性(外見・性別・年齢)を理由に、人の価値を上下づけたり、行動の自由を制限する無意識の差別に当てはまり、固定観念が潜んでいます。
友人との会話、職場でのやりとり、家族との日常。知らず知らずのうちに使っていたり、耳にしていたりしませんか?よかれと思って発した言葉が誰かを傷つけたり、自虐のつもりで使っていた言葉が自分自身の自己肯定感を下げることになっているかもしれません。
この記事では、「聞いたことはあるけど、よくわかっていない」3つのキーワードについて解説します。
ルッキズムとは
容姿を基準に人の価値を測り、差別や偏見を生み出す考え方──それが「ルッキズム」です。1970年代のアメリカで生まれた言葉で、英語の「look(外見)」と「ism(主義)」を組み合わせたもの。日本では「外見至上主義」とも呼ばれています。
近年、この言葉が注目される背景にあるのがSNSです。InstagramやTikTokで誰もが「見られる」環境が当たり前になり、他人より見栄えよく、褒められるような写真を撮りたいと感じる人が増えています。いいねやフォロワー数が、まるで自分の価値を測る物差しのようになっているのです。また、二重まぶたや脱毛の広告、細身のモデルばかりが目に入ることで、「そうでなければ綺麗じゃない」というプレッシャーも生まれています。
これは、SDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」にも関連する問題で、多様性を大切にする考え方が浸透しつつある今、私たち一人ひとりが自分の言動を見直すことが求められています。
よくある発言例
「二重だったらもっと可愛いよ」
「痩せたら絶対かわいくなる」
「丸顔だから優しそうに見えるよね」
「あの俳優、昔はイケメンだったのに太ったね」
「痩せたらかわいい」と言われれば、「今の自分はダメ」と感じ、そこから極端なダイエットを始める人も少なくありません。褒めているつもりの発言だったとしても、その言葉が相手にどう届くか、想像することが大切です。
なぜ問題?ルッキズムが生む、心と社会への影響
「外見が優れていれば価値がある」という物差しが社会に広がれば、その人が持つ才能や性格、努力を軽視することにつながります。
精神面への悪影響も見逃せません。容姿へのこだわりが過剰になり、食事を極端に制限する摂食障害や、自分の外見を異常に嫌悪する「醜形恐怖症」に悩む人もいます。また、就職の場面で「顔採用」という言葉があるように、本来無関係なはずの場面で容姿が選考基準になるケースもあります。実力ではなく見た目で判断される不公平が常態化すれば、社会全体にとってもマイナスです。
ルッキズムは、私たち一人ひとりの無意識の言動から生まれています。自分の言葉を振り返ることが、問題解決の第一歩です。
ミソジニーとは
「ミソジニー」は、女性という性別を理由に、嫌悪感を抱いたり軽んじたりする態度や思想のことを指します。言葉のルーツは古代ギリシア語で、「misos(憎悪)」と「gune(女性)」を組み合わせたもの。直訳すれば「女性憎悪」となります。
ここで重要なのは、これが単なる個人の感情ではないということです。背景には「男性が上位、女性が下位」という社会に染み付いた価値観があります。「家事育児は女性の役目」「女性にリーダーは務まらない」といった固定観念が、ミソジニーを支える土台になっているのです。
さらに注目すべきは、男性から女性へだけでなく、女性から女性へも向けられる点です。社会の中で無意識に植え付けられた価値観によって、女性自身が女性を否定してしまう。それがミソジニーの持つ構造的な問題なのです。
よくある発言例
「女に管理職は向いてない」
「女の人って論理的な会話できないよね」
「女は体温が高いから、寿司職人に向いてない」
「私、女子力ないから」
「女性専用車とかレディースデーとか女ばっかり優遇されてる」
「あの人が出世したのって、上司と寝たからじゃない?」
これらの発言の根底には、「女性とはこういうもの」という思い込みがあります。実際にそれは個人の性格や能力ではなく、性別だけを理由に判断してしまう。それがミソジニーの典型的なパターンです。
最近ではジェンダー平等を求める声が大きくなっていますが、古い価値観はまだ完全には消えておらず、職場や学校、家庭の中で形を変えながら残り続けています。
言葉だけじゃない、ミソジニーの深刻な影響
ミソジニーは、言葉の問題にとどまらず、実際の暴力や社会的不平等を引き起こします。ユニセフのデータによれば、世界の女性の約3人に1人が人生のどこかで身体的・性的暴力を経験しているとされます。こうした暴力の背後には、女性を支配してもよい存在だと考える思想が潜んでいます。
雇用の場面でも格差は明らかです。日本の職場では管理職に占める女性の比率が依然として低く、厚生労働省の令和5年調査では、男性の賃金を100とした場合、女性は約75という結果が出ています。会議で女性の意見が軽視されたり、女性が家事労働をするものというジェンダーバイアスはまだ根深く残っています。
こうした不平等は個人の意識だけでなく、メディアの描写や家父長制の強い文化にも原因があります。一人ひとりの意識改革と、社会の仕組みそのものを変える取り組みが必要です。
エイジズムとは
年齢だけで人を評価し、可能性を制限してしまう偏見または差別──それが「エイジズム」です。1969年にアメリカの老年学研究者ロバート・ニール・バトラーが提唱した概念で、年齢を理由にした偏見や不当な扱いを指します。
「もういい年なんだから」「その年齢でそんなことするの?」といった何気ない言葉や、物忘れをした人に「年だからね」と決めつけることも、エイジズムの一例です。
特に女性は「若さこそ価値」というメッセージを受けやすく、年齢を重ねることがネガティブに捉えられがちです。また、エイジズムは他人だけでなく自分自身にも向けられます。「もう若くないから」と挑戦を諦めるのも、内面化されたエイジズムの表れです。
老年学者エルドマン・パルモアは、エイジズムを人種差別、性差別に次ぐ「第三の重大な差別」と位置づけています。
よくある発言例
「その歳でミニスカート履くの?」
「20代のうちに結婚相手見つけないと厳しいよ」
「私おばさんだから〜」
「あの年で結婚してないのは、絶対性格に問題あるよね」
「この年齢から資格取っても意味ないでしょ」
ときに、エイジズムと捉えられる言葉は励ましや心配として発せられることもありますが、受け取る側には「年齢を理由に可能性を否定された」と感じられる場合も。特に女性に対しては、容姿や結婚、出産といったトピックでエイジズム的な発言がされやすい傾向があります。
年齢はあくまで数字であり、その人の能力や魅力を決めるものではないはずです。
エイジズムが、「未来の自分」を苦しめる
年齢を理由に挑戦が妨げられたり、医療や住居へのアクセスが制限されても「高齢だから仕方ない」と片付けられてしまうことは人権侵害です。
医療や介護の現場で高齢者に敬語を使わず、子どもに話しかけるような口調で接するケースも問題視されています。そして何より、エイジズムは「未来の自分」を苦しめます。今、若い人が高齢者を年齢で判断する社会は、やがて自分自身が同じことをされる社会になるのです。
世界ではエイジズム対策が進んでおり、EUは2006年に年齢差別を禁止する法律を制定、アメリカも1967年に「雇用における年齢差別禁止法」を制定しています。年齢にとらわれず、一人ひとりが尊重される社会は、私たちの意識と行動で実現できる未来です。

普段の生活の中で、これらに当てはまる言葉を耳にしたり、口にしたことはありましたか?
「ルッキズム」「ミソジニー」「エイジズム」──これらはすべて、日常に潜む偏見や差別です。
悪意がなくても、無自覚にでも、私たちは誰かを傷つけ、可能性を奪ってしまうことがあります。そしてその何気ない発言は、自分自身の自己肯定感もじわじわ削っていくのです。
でも、知ることは変わることの第一歩。
これらの言葉は、社会の問題でもあるのです。無意識のうちに「女性は〜するべき」「男性は〜であるべき」という価値観が刷り込まれ、これらの発言が生まれています。
でも、これらを知っていれば、発言する前に立ち止まることができます。そして、自分自身や他の誰かを傷つけないように、言葉を選べるようになるのです。「この言葉、相手はどう受け取るかな?」と想像すること。その小さな積み重ねが、誰もが生きやすい社会をつくっていきます。
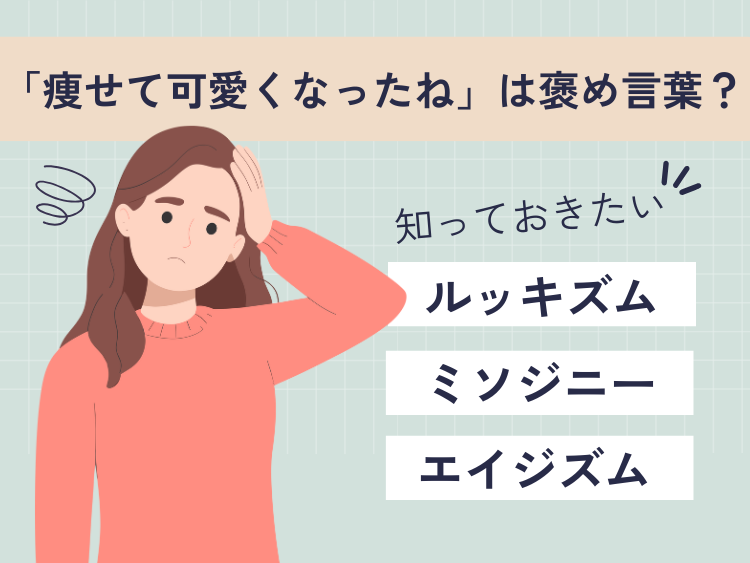







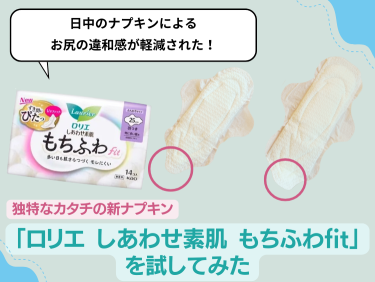



![YES インティメイト・ウォーターローション WB[さっぱり保湿ケア]](/assets/media/2022/02/1721113748052-375x375.jpeg)