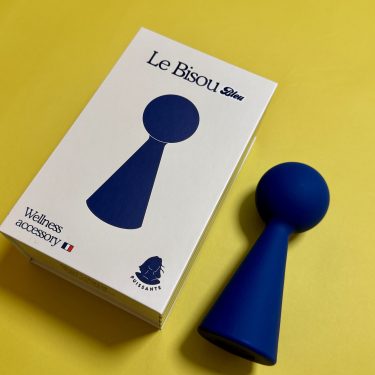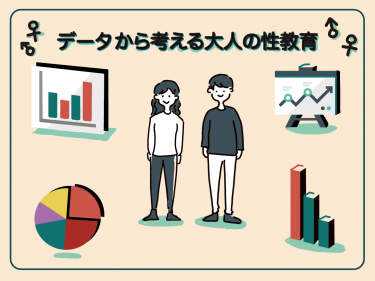生理のたびに生理痛を経験している人は約30%であり、ときどきある人も含めると80%以上の人が生理痛を経験しているというデータがあります。
女性の社会進出が推進されるなか、労働基準法では生理日の就業が著しく困難な女性に対して生理休暇の取得を認めています。
しかし、生理休暇の取得率は1%を切るなど低い数値となっています(厚生労働省の調査より)。
その原因として、生理休暇に対する認知度が低い、正しい認識がない、職場の雰囲気で申請しづらい、生活への影響などが挙げられます。
今回は、生理休暇を正しく知るために、労働基準法における生理休暇の定義や有給・無給の取り扱い、申請方法などの基礎知識をご紹介します。
生理休暇とは?
生理休暇は、労働者の権利として1947年に労働基準法に盛り込まれた制度。第68条に「生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合には、その者を生理日に就業させることはできない」と記されています。
生理日の就業が著しく困難な女性とは、生理による体調不良(下腹痛、腰痛、吐き気、めまい、頭痛等)により就業が困難な女性と定義されています。
生理休暇の取得率は1%以下
厚生労働省の調査によると、2014年4月~2015年3月末に生理休暇を1日でも請求した人がいた女性従業員の割合は0.9%と低い結果となっていました。
全労連の調査では、生理休暇をとれない理由(複数回答)について聞いたところ、最も多かったのは「人員の不足や仕事の多忙で職場の雰囲気としてとりにくい」という回答でした。2番目は「苦痛ではないので必要ない」、3番目は「恥ずかしい、生理であることを知られたくない」が挙げられました。
生理休暇を取得しやすい環境形成には、職場全体としての生理に対する正しい認識が必要であることが調査結果から読み取れます。
正規雇用に限らず、誰でも取得できる
生理休暇は、生理による体調不良(下腹痛、腰痛、吐き気、めまい、頭痛等)により就業が困難な場合に申請すれば、誰でも取得できます。正社員だけではなく、パートや契約社員、派遣社員などどのような契約でも認められます。
「アルバイトだから、生理休暇は使えない」「就業規則に生理休暇の対象者が限られている」など、就業規則で生理休暇を取得できる従業員の範囲を限定することは労働基準法違反となります。
生理休暇を取得できる日数は?
生理期間の痛みは、人によって大きく異なるため、生理休暇の日数は企業によって定めることはできません。「生理休暇は月に1度までとする」など企業が就業規則などにより生理休暇の日数を限定すると、労働基準法違反となります。
また、休暇の請求は、必ずしも暦日単位で行う必要はなく、半日又は時間単位で請求された場合は、企業はその範囲内で就業させればよいとされています。
生理休暇中の給与はどうなる?
生理休暇は法律に定められていますが、有給か無給かについての規定はありません。そのため、ここは企業によって異なる点です。
たとえば、生理休暇を年次有給休暇に割り当てたり1日目は有給、2日目からは無給という扱いにすることも可能です。
東晶貿易株式会社が運営するキャリア転職センターによる「生理休暇の実態に関する市場調査」では、生理休暇を有給で取得が68%、無給で取得は32%でした。
同じ調査の中で、生理休暇を使用できない理由のひとつとして「無給であると生活に影響が出るため使用できない」という回答がありました。生理休暇中の給与について、あらかじめ雇用契約書や職場の方針を確認しておくといいでしょう。
生理休暇の申請方法は?
生理休暇の申請は、正確な生理日や、生理による体調をあらかじめ予測することが難しいことから、当日に口頭で申し出ても良いとされています。そのため、医師による診断書などを提出して証明する必要はありません。
日本企業における生理休暇の取得率(1%以下)が著しく低い原因には、「生理休暇が法律で定められていることを知らなかった」「男性が多い会社のため取得しづらい雰囲気」「無給のため生活に影響が出て取得できない」などさまざまな理由が挙げられます。
女性の社会進出が進められるなかで、企業が必ず向き合わなければならない生理休暇。私たちひとりひとりも、自身の体と向き合い、国が定めた制度を知り、ときには周りを巻き込みながら、働きやすい環境を作っていくことも大切なのかもしれません。




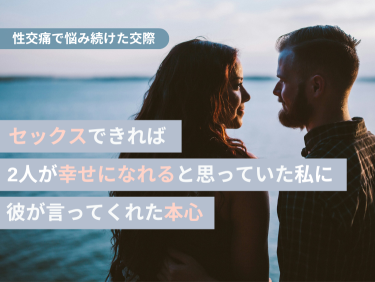
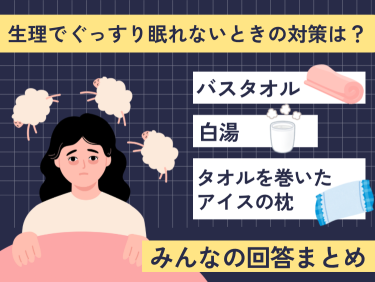


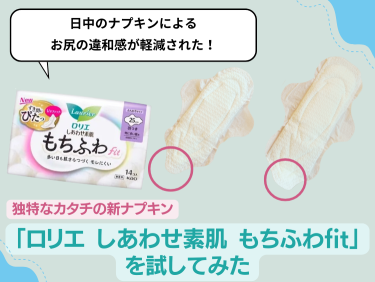




![YES インティメイト・ウォーターローション WB[さっぱり保湿ケア]](/assets/media/2022/02/1721113748052-375x375.jpeg)