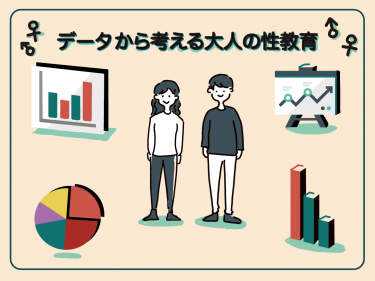ランドリーボックスは、外陰部の構造を楽しく正しく理解し対話するためのパペットとしてBa-Vulva(ばあばるば)を企画制作しています。
ばあばるばでは、正しい情報を知り、対話を通じて健やかな日々を送っていただきたいという想いから、<Ba-Vulva Friend>と題し、国内外の性教育やセクシュアルヘルスの専門家にインタビューを行っています。
今回お話を伺ったのはSRHR(Sexual / Reproductive Health and Rights 性と生殖に関する健康と権利)を推進する活動を行う一般社団法人SRHR Japanの代表理事を務める池田裕美枝先生です。
産婦人科医師としての経験を活かしながら、臨床現場と社会をつなぐさまざまな取り組みを行っています。今回は、SRHR Japanの活動内容や、日本社会におけるSRHRの課題についてお話を伺いました。

医療と福祉を結ぶ「KYOTO SCOPE」
—— SRHR Japanの活動について教えてください。
SRHR Japanは、SRHRの概念を日本に根づかせるために立ち上げた一般社団法人です。活動は大きく分けて三つあります。
一つ目は「SRHR Initiative」で、国連人口基金(UNFPA)が毎年出している世界人口白書の日本語版の翻訳および監訳に携わっています。SRHRは国連が推進しているものですが、そのまま日本の文化に当てはめるのは難しい面があります。
例えば、人権以前に「個人の自分」という考え方の概念が欧米と日本では違います。これは日本だけでなく、どの文化にもそれぞれ社会と自分との関係性の捉え方があります。
そのような中で、SRHRをどういう言葉でどう伝えていくべきか、どんな実践があるのかをディスカッションする場がSRHR Initiativeです。
公開勉強会だけでなく、内輪の勉強会も積み重ねています。哲学者や法学者など、いわゆる学際的な交流をしています。
—— 国内でそのような機会はなかなかないですよね。
はい、日本にはSRHRを旗印に掲げた研究室がないんです。私はイギリスでSRHRのディプロマコースを取得しましたが、日本ではそのような場所がなかったので、大学にそのような場所を作りたいと思っていました。
そこで、京都大学の学際融合センターの研究・教育グループを支援するライトユニット制度を活用してSRHR研究会を立ち上げました。京都大学内外のいろんな研究者や医師の友人たちと集まり、学び合う場を作っています。
—— 他にはどのような活動がありますか?
二つ目は、医療と福祉を結ぶ「KYOTO SCOPE」という活動です。
産婦人科の医療現場ではいろんな社会背景を持つ方々に出会います。例えば若年妊娠や多産、妊婦健診に来ない方、性感染症を何度も繰り返す方など、一見するとSRHRの課題のように見える方々です。
でもこれは単に「知らないから」ではないんです。社会的に排除されていたり周辺化されていたりして、自分のことを大事に思える基盤がなく、自傷行為を繰り返すように生きている方々もいます。
繰り返す中絶も、その背景に自己否定的な生き方がある場合には、避妊法を教えるだけでは響かない。そういったことを臨床現場で感じて、医療と福祉を結ぶ場として「KYOTO SCOPE」を立ち上げました。
—— 「KYOTO SCOPE」はどのような架け橋になっているのでしょうか?
「KYOTO SCOPE」はウェブサイトを軸にオンラインで人の繋がりを作る場です。医療現場は忙しく、患者さん一人に対して5分も時間が取れないことも多い。その中で社会背景を聞くのは、パンドラの箱を開けるようなものなんです。
一方で、病院の外に出ると、京都市内にも心優しい支援者の方々がたくさんいることに気づきました。NPOの方や行政の方など様々ですが、医療者とは違うタイムスパンで支援を必要としている方に関わってくれる方々がいます。
そういった支援者の方々と医療者をつなぐため、「KYOTO SCOPE」では「このケースだったらこんな機関もが助けてくれる」というソーシャルワークの事例を提示しています。

—— 支援機関との連携はどのように行っているのですか?
「KYOTO SCOPE」では、支援機関の方々と直接連絡を取りあい、繋がりを作っています。その中で、専門家の方々から別の方をご紹介いただくことも多いです。
「KYOTO SCOPE」のサイトにケーススタディとして支援の方針なども含めて提示していますが、ある時、その情報をみた現場の支援職の方が「この人をここに繋ぐのは適切ではない」と教えてくれたことがありました。
アルコール依存症の方の繋ぎ先として、ある当事者団体の情報を掲載していたのですが、アルコール依存症において、女性の場合はDVの被害者であることも多く、男性の場合は加害者であることも少なくないため、男女別々にピアカウンセリングをした方が良い場合が多いのですよね。
なので、依存症の場合には、当事者の方が女性の場合は女性がより安心できる場にお繋ぎしたほうがいい、と教えてもらいました。現場の知恵を教えていただきながら、ケーススタディも修正しています。
SRHRは社会的側面を支えること
—— 現場の方からご意見いただけるのはありがたいですね。
はい。この件があってから、3か月に一度、ステークホルダーの方に集まってもらい「このケースについてご意見ください」という会議を開催しています。
グループディスカッションの時間も設けて、他職種の方と交流する機会を作っています。実際の支援においても、どのような人たちが支援をしているのか、顔が見える関係になることで、適時適切な支援が可能になると思っています。
あとは「おてらでトーク」という交流会を年に1度開催しています。
名前の通り、お寺で開催していますが、テーマとしては「若年女性の孤立孤独と社会的処方」「日本で暮らす外国人の社会的つながりを考える」など、毎回難しいケースについて話し合いながらも、開放感のある空間でほっとできる場にしています。
勉強会やケースディスカッションの後は、お抹茶で一息つきながら茶話会をします。研究者や現場の支援者、学校の先生、行政の方、NGOの方など様々な方が参加しています。


—— ケースカンファレンスも「おてらでトーク」も多くの職種の方があつまっていますね。みなさんSRHRを拡げたいという想いで集まっているのでしょうか?
集まってくださっている方の共通項は「若い人を支える取り組みをされている」ことであって、もしかしたらSRHRという意識は皆様にはないのかもしれません。
でも、私はKYOTO SCOPEの取り組みを、SRHRの社会的側面を支えることだと強く思っています。
まず自分自身を大事に思える基盤を作ること。自分と対話できる「私が私と対話するに値する人間なんだ」と思えることが大切です。
自分と対話できて初めて、SRHR(性と生殖に関する健康と権利)についての話を始めることができるのです。
しかし、それには自分が安全であることが前提になりますよね。明日の食事に困っている人は自分と向き合う余裕すらないはずです。
高齢者や福祉支援は社会制度も整ってきてカンファレンスも多く、制度化されてきていますが、若い人に対する支援制度はまだ整っていません。まだ制度はないけれど、支えようとしている人たちはたくさんいます。
そして社会が階層化した格差社会の中で、しんどい状態の方は本当にしんどく、困難は重層化しています。
たとえば、依存症で発達障害で海外の方など、重なれば重なるほど依存症支援施設では対応しきれなくなる。じゃあ他の施設を知っているかというと意外とみなさん知りません。
だからこそ、このような出会いの場、横と繋がれる場が大切なんです。

—— 池田先生はクリニックでも若い世代に向けた取り組みをされていますよね。
はい、三つ目の活動が「ユースクリニック」です。大学で授業を担当していることもあり、学生たちが学んだことを自分たちで他の人にシェアする場として、クリニックを開放しています。
学生たちが集まって自分たちで考えた展示物を作り、発信する場になっています。
彼女たちはごく一般の大学生ですが、「情報化社会でなんでも知っていると思っていたのに、こんな大事なこと知らなかったんや」と驚いている姿をみると、私たち専門家の胸にも深く刺さるものがあります。
—— 学ぶだけでなく自分の言葉で伝える対話の場もとても貴重ですよね。学生さんたちにとっても貴重な機会ですね。
そうですね。2024年3月には、UNFPA(国連人口基金)の事務局長が来日し、私たちのクリニックを訪問してくれました。学生たちが英語や日本語でプレゼンテーションをし、自分たちの声を直接届ける機会になり、とても貴重な経験でした。
最初は私たちが学生たちをサポートしていましたが、今では自分たちで大学のカフェルームでHPVワクチンについて話したり、高校に行って性の話をしたりと、自主的に活動を広げています。

日本社会におけるSRHRの課題
—— SRHRという言葉をそのまま日本文化にあてはめるのは難しいというお話もありました。SRHRを日本に根づかせるにあたり、どのような課題があると感じていますか?
「My body, My choice(私の体は私のもの)」という考え方は大きなキーワードだと思いますが、日本文化では難しい面があります。
というのも、日本では「相手がどう望んでいるか」を汲み取り「こうした方が相手は喜ぶかな」「このままでは信頼関係が崩れないかな」という視点で決めていくことが多いように感じます。
例えば、診療でも医師から「この治療でどうですか」と言うと、患者さんは内心は嫌だと思っていても「はい、そうします」と答えることがあります。
なぜなら医師との関係性を悪くしたくないからです。これも自己決定ではありますが「My body, My choice」とは少し違いますよね。
—— そうですね。確かに、相手との関係性から意思決定をする人は多いように感じます。
でも中絶を例にすると、私の経験では「私は産みたいけれど、彼が堕ろせと言うから中絶します」という人はほとんどいません。
迷っている人はたくさんいますが、そういう時に「自分が決めた」と思えないと後悔することになります。だから「自分で決めてね、どんな選択も応援するから」と伝えるようにしています。
ほとんどの方は、しっかり自分と向き合って決めてから診察室に入ってきてくれますが、中にはどうしても決められない人や、自分と向き合うことを初めから放棄している人、自分の人生に責任を持つ勇気が持てない人もいます。
—— そのような場合は、どうするのでしょうか?
そういう方々には、その人の行動や反応の背景にトラウマ(心的外傷)の影響があるかもしれないということを前提とした「トラウマインフォームドな視点」で寄り添う支援が大切だと考えています。
日本社会では「自分自身と向き合う」という一呼吸が大切だと思います。
自分が決めたのか、相手が決めたのか、相手との関係性で決まったのかというよりも「自分はどこにいる自分だったら自分なのか」という視点が重要です。
ただ、そういう自分との対話に慣れていないと、いざという時に何をすべきか分からなくなってしまいます。
—— 対話に慣れる。性教育の重要性についてはどう思われますか?
若い頃から教育することが大切です。性教育といっても生殖の仕組みだけでなく、相手を尊重する、自分を尊重するとはどういうことか、どんなコミュニケーションスキルが必要かを学ぶことが大切です。
私が尊敬している「生きる教育」という取り組みがあります。これは「生命の安全教育」のモデルになった大阪市立生野南小学校(現田島南小中学校)の「性・生教育」です。
この学校は養護施設の子どもたちが多く通う小規模な学校で、かつては荒れていて、喧嘩も多い状況でした。教員の方々がトラウマインフォームドケアと出会い、心理回復プロセスのグループ面談を授業に取り入れたいと始まったのが「生きる教育」です。
「生きる教育」は、国語教育とセットで行うのが大切とされていて、国語の授業で感情を表現する力を育てています。
例えば「うざい」と言われるだけなら喧嘩になるかもしれませんが、その感情のことを「心がえぐられるくらい辛い」とか「自分は正直少し不快に思った」など、多様な言葉で表現できれば、暴力は遠のくかもしれません。
さらに、生きる教育では子どもの権利や関係性の作り方、生殖の仕組みや将来の描き方、または対話そのものを体験授業として学んでいきます。
この「生きる教育」は9年かけて成果を上げ、学力も平均以上になりました。今は小学校1年生から中学3年生まで一貫したカリキュラムがあるんですが、実はこのカリキュラムを見ると、ユネスコの包括的性教育のガイダンスとそっくりなんです。
「生きる教育」として実践されていたものが、結果的に包括的性教育につながっていたんです。
大阪市立生野南小学校 小野太恵子氏へのインタビュー(SRHR JAPAN)
自分の身体を知ることの大切さ
—— ランドリーボックスでは、外陰部の構造を学ぶためのパペット「Ba-Vulva(ばあばるば)」を制作しています。構造を理解することは大切でしょうか?
たとえば外陰部の痛みがある人にとっては、自分の体の構造を知ることは必須です。トラブルがなく快適に生きている人もいますが、様々な悩みを抱える方もいます。
以前「日本の性教育では『ここは大切なところだから、人に触らせちゃいけない、自分でも触ってはいけない』と教えている人がいる」と聞きましたが、それはあまりにおかしいですよね。
実際に、自分で触ったことがなくて、産婦人科医と彼氏しか触ったことがないという女性もいます。中には見るのが怖いという方もいます。
70歳の女性に内診の前に、「これ(外陰部)にすごく罪の意識があってずっと悩んでいる」と相談されたことがあります。
すごく厳格な家庭で育ち、思春期の頃から自分の体に触れることに罪悪感を覚えていたようで「誰にも見せられない、内診なんてできない」と思われていました。
外陰部やクリトリス、オーガズムの解剖学的、科学的な知識をお伝えすると、「なあんだ、そんなことか」と思うようなことですよね。

—— 思春期のときにどのように教わったか、認識したかが長く影響するんですね。罪悪感をなくしていくにはどうしたらいいのでしょう。
私のクリニックでは性機能外来という自費診療もありますが、一般外来でも性の相談をする方が多いです。
例えば「ちょっと濡れにくいんですけど、これって普通なんですか?治療したら治るものなんですか?」という相談はとても多いです。
みんな普通かどうかが知りたいんですよね。LINE相談などにも「色が普通じゃない気がする」「小陰唇が長い」「形がおかしいのでは」といった悩みが寄せられます。
おそらくアダルト動画などを見て比較してしまうんでしょう。そうやって悩んで、最終的に「手術します」というような話になるケースもありますが、それが本当にその人にとって必要なことなのか。自分で納得して決められているのかが重要だと思います。
—— このようなパペットについてどう思われますか?
臨床現場において、このような立体的な教材はとても使いやすいと思います。実際に説明する時に、平面的な説明より立体的な方が分かりやすいです。
婦人科だけでなく皮膚科など外陰部を診る医師にとって役立つかもしれません。
例えば外陰部に病変があって薬を塗る場所を説明する際に、口頭で「〜〜に塗って」と伝えるよりも実際に場所を示しながら説明できますよね。患者さんにとっても親しみやすく理解しやすくなります。
あとは洗い方を説明するときなども使えますし、女性自身が自分の体を理解するのにも役立ちますね。
池田先生、ありがとうございました!
SRHRを日本に根付かせるためにはどうすればいいのか?
SRHRが社会に根付き、それぞれがSRHRを本当の意味で理解し、自分や相手を尊重するには、単に言葉を認知させるだけでは難しい。
大切なのは「自分自身を大切に思えること」。そのためには、安心して暮らせる社会基盤が不可欠です。
だからこそ、SRHR Japanの活動のように、医療と福祉、そしてさまざまな専門家が連携し、多様な視点で人々に語りかけ、ケアを広げていくことが求められています。
一人ひとりが自分と向き合い、本当の意味で「My body, My choice(私の体は私のもの)」といえる社会へ。
ばあばるばのプロジェクトも、SRHRの実現に向けて、私たち一人ひとりができることを改めて考えていきたいと思います。
お話を伺った方

池田 裕美枝先生
産婦人科専門医、社会医学系専門医、内科認定医、医学博士。京都大学医学部卒業。総合内科研修後、産婦人科に転向。女性のヘルスケアに身体的、心理的、社会的にアプローチする仕事を心がけている。医療法人心鹿会海と空クリニック京都駅前院長。神戸市立医療センター中央市民病院女性外来担当
ーー
本記事はランドリーボックスが制作している性教育パペット「Ba-Vulva(ばあばるば)」の公式サイトの記事を一部編集の上、転載しています。
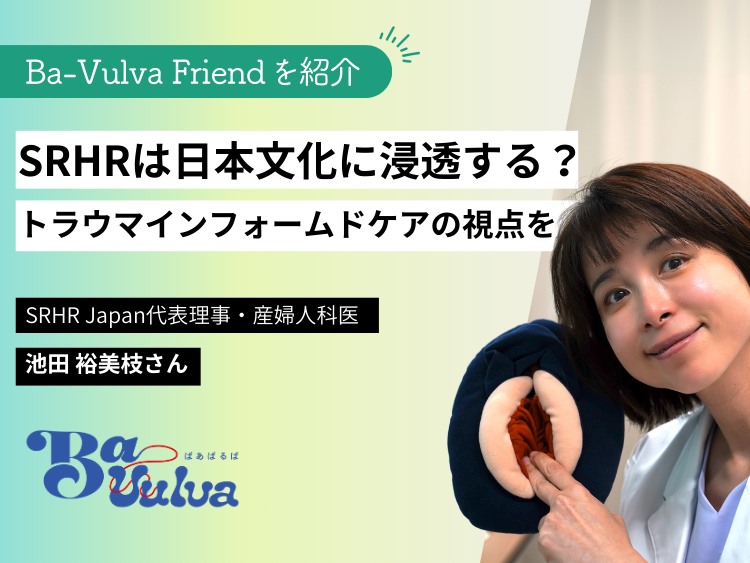

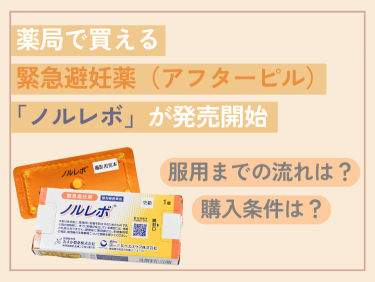





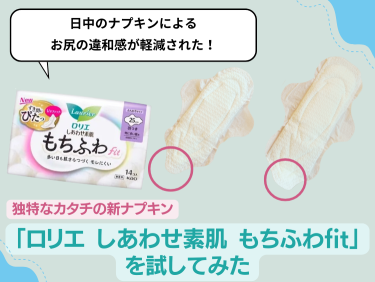



![YES インティメイト・ウォーターローション WB[さっぱり保湿ケア]](/assets/media/2022/02/1721113748052-375x375.jpeg)