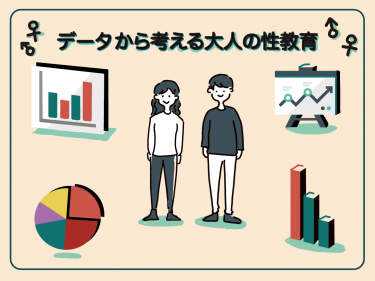SNSやインターネットが普及した現代、子どもたちが自分の体や心を理解し、安心して生きていくためにも学校教育における「性教育」の重要性が訴えられている。
体や性の知識にとどまらず、人権を軸とした「包括的性教育」が国際的な標準だが、日本ではいわゆる「はどめ規定」によって十分な指導ができない現状がある。
さらに、どこまでを規定の範囲とするかは学校や教員によって異なり、教育現場で悩みを抱える声も少なくない。
2027年に、10年に1度行われる教育指導要領の改定を前に、「はどめ規定」の撤廃署名のキックオフシンポジウムが開催された。同シンポジウムは、「〝人間と性〟教育研究協議会(性教協)」などが主催し、各専門家らが学校現場の現状を共有した。
登壇者には、教育評論家の尾木直樹さん、NPO法人ピルコン代表の染矢明日香さん、そして長年中学校で性教育に取り組んできた樋上典子さんが並んだ。
シンポジウムのコーディネーターを務めたのは、「#なんでないのプロジェクト」代表の福田和子さん。
それぞれの経験や視点から「はどめ規定」がもたらす課題と今後の性教育のあり方について語り合った。
<2025年12月2日追記>
2025年11月27日、『はどめ規定』撤廃署名活動実行委員会は、4万2759筆の署名を文部科学省に提出した。

当日は会場が満席、オンラインでは約400名が視聴し、高い関心の集まりを見せた。
包括的性教育の必要性の現状の課題
「包括的性教育」とは、体の仕組みや生殖を学ぶだけでなく、人間関係やジェンダー平等、幸福といったテーマまで幅広く扱い、人権の尊重を基盤にウェルビーイングの実現を目指す教育である。
子どもの発達段階に応じたカリキュラムを用い、科学的に正確な知識を継続的に学ぶことが推奨されている。
一方で日本では、「性教育」という言葉に「生殖」「性感染症の予防」といったイメージが根強い。
国連・子どもの権利委員会は包括的な政策の実施を日本政府に勧告しているが、依然として「寝た子を起こすな」といった風潮が残り、性に関する教育や対話が後ろ向きにとらえられる現状がある。
こうした社会的な空気感の中では、子どもたちが悩みを抱えても大人に相談しづらく、結果として性被害や性感染症の深刻化を招く可能性も否めない。
35年以上にわたり性教育の実践を続けてきた樋上典子さんは、現在も東京都足立区で非常勤講師として授業を行っている。
樋上さんは「子どもたちが変容していく姿も面白いけれど、それ以上に『性の学びは必要だから』。性は思春期だけでなく、一生にわたり向き合うもの。子どもたちに幸せになってほしい。そのためには科学と人権を基盤とした包括的性教育が不可欠です」と語り、その必要性を強調した。
学習指導要領における「はどめ規定」の問題点

樋上さんは、日本の学校で性教育が進まない背景には、いわゆる「はどめ規定」があると指摘する。
いわゆる「はどめ規定」とは、文部科学省が定める「学習指導要領」には、各教科の内容や扱い方を示す基準があるが、その中で「性行為」の扱い方を制限する内容が記載されている。
現在の小学校理科や中学校保健の学習指導要領には「受精に至る過程」や「妊娠の経過」を「取り扱わないものとする」という一文がある。
保健体育科では、「妊娠や出産が可能となるような成熟が始まると言う観点から、受精・妊娠までを取り扱うものとし、妊娠の経過は扱わないものとする」と定められている。
多くの中学生が月経や射精を経験し妊娠可能な年齢に達していても、「性交によって妊娠が成立する」という核心的な仕組みを学ぶことはできない。
樋上さんは「月経がある人と射精がある人が性交渉したら妊娠の可能性があることは教科書に明記されていません。
けれど中学3年生になると性感染症を学ぶ。性交を教えないで、どうやって子どもたちは理解するのでしょうか」と矛盾を指摘する。
さらに高学年の理科で「受精」を学ぶ際も、例として用いられるのはメダカである。メダカは水中で受精するため、「お風呂の中で妊娠してしまうのでは」と誤解する子どもがいるという。
「幼い子どもが性的虐待に遭い、勝手に性器を触られても『何が起きたのか分からない』となってしまうのは当然だと思ってしまいます」と正しい知識が欠如している危うさを訴えた。
「はどめ規定」の誤解と指導者の忖度

2020年、文部科学省の局長は「はどめ規定は決して『教えてはならない』というものではない。必要と判断されれば学校や個別の指導で扱うこともできる」と発言している。
しかし実際には「発達段階の考慮」「学校内の共通理解」「保護者や地域の理解」「集団指導と個別指導の区別」といった条件が付されており、現場の判断に委ねられる余地が大きい。
そのため、学校ごとに解釈が異なり、指導内容の統一がなされていない。
NPO法人ピルコンの染矢さんは、全国の中高で講演を行う中で、「『緊急避妊は性暴力の延長だから伝えてよい』と判断する人もいれば、『コンドームの図示は刺激になるから禁止』とする人もいる」と現状を語る。
学校の管理職や地域の教育委員会の意向によって大きく左右され、結果的に「はどめ規定」が統一的な基準として機能していないことが問題だと強調した。
さらに2021年からは、子どもを性の被害者・加害者・傍観者にさせないことを目的とした「生命(いのち)の安全教育の推進」が始まった。しかしこの教材も学習指導要領に基づいて作成されているため、十分な理解につながるのか課題が残る。
子どもたちの性に関する知識不足と誤った情報へのアクセス
学校で体系的に学ぶ機会が限られる一方で、心身の発達とともに子どもたちの性への関心は高まっていく。日本財団の調査によれば、性行為に関する知識の入手先として最も多かったのは「友人から」で47.4%。
男子に限ると、学校の授業よりもアダルトサイトから情報を得ている割合のほうが高いという結果が出ており、正しい情報に基づいた理解が十分に確保されているとは言い難い。
「はどめ規定」が設けられた1998年当時、インターネットやSNSはまだ普及していなかった。しかし現在は、子どもたちが真偽不明の情報に触れる機会が格段に増えている。
染矢さんは「幼いからこそ、正しいかどうかも分からないネット上の情報に左右されるのではなく、信頼できる情報から学ぶことが大切」と強調する。
「大人から見ると『うちの生徒は幼いから』『性的な関心はまだ低い』と思えるかもしれませんが、それは学校の先生など限られた視点での話です」とも指摘した。
実際、ピルコンにはセックスに関する疑問のほか、性的画像のやり取りや妊娠の可能性について親に相談できずに悩む声など、多様な相談が寄せられている。子どもたちが安心して学べる環境が十分に整っていない現状が浮かび上がった。
教員による性暴力・性犯罪の問題と背景

現在の性教育の現状について「いまだに『寝た子を起こすな』という議論が聞こえてきます。しかしこのSNS時代に寝ている子どもなんて1人もいません」と語ったのは、教育評論家で一般社団法人包括的性教育研究協議会代表の尾木直樹さん。
尾木さんは、子どもたちの知識不足に加えて、学校や大人の側にも深刻な問題があると指摘した。
2023年度には性犯罪や性暴力で懲戒処分を受けた教員が過去最多の320人にのぼり、問題の深刻さが浮き彫りになった。教員免許の失効者を管理するデータベースも十分に活用されておらず、「抑止力にはなっていない」と批判した。
「学校は本来、子どもにとって安心・安全の場であるべきなのに、性被害が繰り返されている。相談窓口の周知も徹底されていない現状は深刻だ」と訴えた。
また、大人自身が性に関する知識を十分に持っていない点も大きな課題だという。性的同意やグルーミングといった概念は社会に広がりつつあるものの、保護者や教員を含め、十分に理解している人はまだ少ない。
尾木さんは「性教育はいやらしい話ではなく、生きることを学ぶ教育。包括的性教育は基本的人権であり、国際的には常識です」と強調した。
9割以上の生徒が性教育が必要だと回答
樋上さんは、大学教員とともに包括的性教育の検証授業を継続してきた。事前・事後アンケートやクイズ形式、グループワークを取り入れることで、最初は照れていた生徒たちの姿に次第に変化が表れたという。
「避妊や中絶の授業は必要か」という問いには、毎年9割以上が「必要」と回答し、「生きていくうえで欠かせない」「知らなければ困る人が出てしまう」といった声も上がった。
授業の効果は、知識の定着だけにとどまらない。
友達と考え合うことで「自分だけではない」と実感でき、いたずらにズボンを下ろすといった行為も激減。性の悩みも「相談してよい」と思えるようになり、安心できる学校生活につながった。
さらに、授業を見学した教員からは「自分自身が生きやすくなった」との声も寄せられている。
包括的性教育は、単発の授業や教材ではなく、発達段階に合わせて継続的に学んでいくことが大切だ。妊娠や性感染症のリスクを減らすだけでなく、性的虐待の防止や、性的マイノリティの子どもたちが安心して過ごせる環境づくりにもつながる。
染矢さんは「自分らしくあっていいんだ、と実感できる自己肯定感の向上も調査で確認されています」と話す。
2027年の学習指導要領改訂に向け署名10万件目指す
今後に向けては、学習指導要領の改定や「命の安全教育」の充実に加え、性的同意やジェンダー平等、多様性の理解を組み込むことが求められる。
その第一歩として「はどめ規定の撤廃」が重要。染矢さんは「いろんな立場や考え方があるが、まずは『はどめ規定をなくす』という共通の目標で連携していけたら」と強調した。
また、SNS時代の性教育をめぐっては誤情報やヘイトが拡散しやすい現実がある。「冷静に情報を見極め、デマに加担しないことが大切」と染矢さん。
さらに「リアルなつながりを大切にし、地域のコミュニティや議員など身近な人に声を届けていくことが、社会全体に『性教育はみんなの課題』という認識を広げる力になります」と語った。
現在、はどめ規定の撤廃を求める署名はすでに 2万筆以上集まり、1日で1500〜2000筆が増える勢いを見せている。
短期間でこれだけの賛同が寄せられていることは、子どもたちが性の被害から守られ、自分らしく生きられる環境を求める声の大きさを示していると言える。
本シンポジウムの最後に、主催でもある“人間と性”教育研究協議会(性教協)代表幹事の水野哲夫さんは、2027年の教育指導要領改定に際し、性教育の「はどめ規定」を議論にあげるにはインパクトのある数字で世論を提示する必要性を語った。

大人たちもまた、性にまつわる正しい知識を学び、人権意識を育むために包括的性教育は欠かせない。その実現のためには、「はどめ規定」の撤廃が不可欠だ。「まずは10万件の署名を集めたい」と訴えた。
現在「はどめ規定」撤廃に関するオンライン署名はchange.orgサイトで実施されており、11月末に文科省に届ける予定だという。
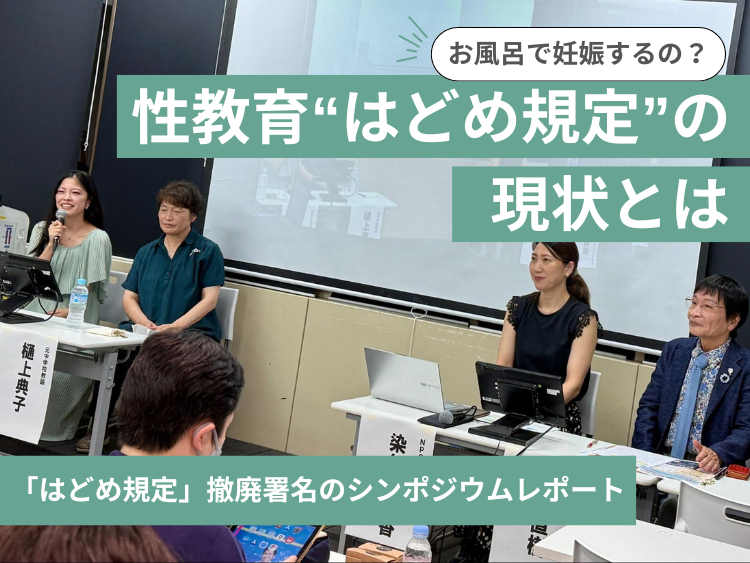

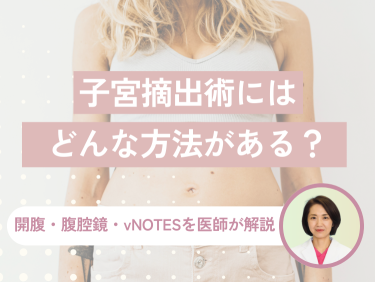
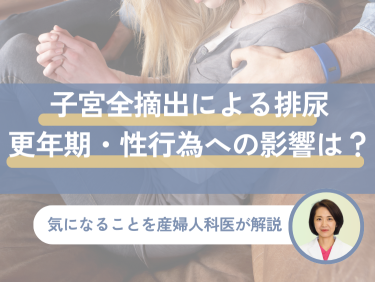
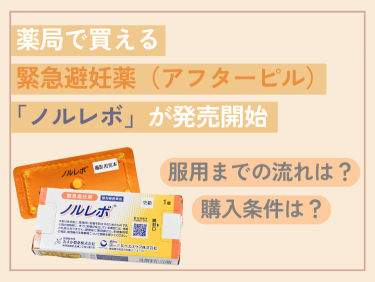



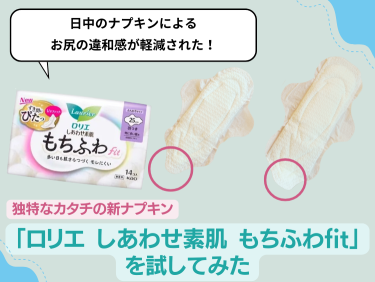



![YES インティメイト・ウォーターローション WB[さっぱり保湿ケア]](/assets/media/2022/02/1721113748052-375x375.jpeg)