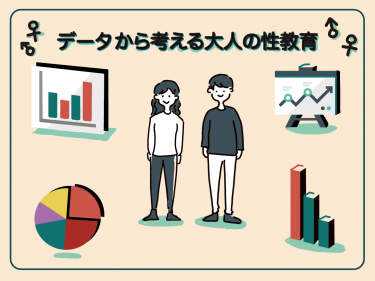【お悩み】これからの季節、インフルエンザやノロウイルスなどが流行しはじめ、コロナウイルスの感染もまだ気が抜けません。秋は行きたいイベントがたくさんあるので、普段の生活から意識して養生できることはありますか?
頻繁に体調を崩す人とそうでない人の差は?
今年は夏場もいろいろな感染症が流行り、治ったと思ったらまた何かに感染し、良くなったと思ったら感染…。また、子どもが感染したあと、家族全員が感染してしまった…。そんな人も多かったのではないでしょうか。
自分自身や周りの人を見ても、しょっちゅう風邪ひいたり、体調を崩したり、毎年インフルにかかる人もいれば、そうでない人もいると思います。
では、その差は何でしょうか?
東洋医学ではその差は『衛気(えき)』にあるとされます。
衛気とはざっくり言えば体の免疫力、バリア機能にあたります。この衛気はウイルスや細菌、花粉、ホコリ、化学物質、気圧、湿度、温度差など体の外から体に悪さをする「外邪(がいじゃ)」から身体を守ってくれています。
この衛気によって全身の皮膚や粘膜にしっかりバリアを張れているかどうかが、感染症にかかりやすいか否かに影響している大きな要因です。
しかし現代人は不規則な生活や食生活の乱れ、運動不足、生活環境などにより、衛気は不足しがちで、皮膚や粘膜の免疫力は低下しやすくなります。
衛気が不足している状態を「衛気虚(えききょ)」と言い、外的刺激の影響を受けやすくなります。具体的には、風邪をひきやすい、疲れやすい、呼吸器系の異常、多汗、季節の変わり目や気温変化に体調を崩しやすいなどの症状が表れます。
衛気不足のチェックリスト
□疲れやすい
□よく風邪をひく
□汗をかきやすい
□やる気が出ない
□鼻水が出やすい
□鼻づまりが多い
□息切れしやすい
□声に力がない
□肌のツヤや弾力がない
□冷・暖房の風が苦手
□咳き込むことが多い
□軟便気味
この中で3つ以上当てはまる人は、衛気が不足していると考えられます。
衛気を高める養生法
それでは衛気を高める食養生、生活養生法をご紹介していきます。
「衛気」を作り、全身に巡らせる臓腑は「脾」と「肺」と言われます。「脾」は胃や腸の消化器系のことで、胃腸が「衛気」を作り、「肺」がそれを全身に巡らせます。胃腸と肺をいたわる養生をご紹介します。
食養生
脾(胃腸)の元気を根本的に補う食養生は「自然の甘味がある黄色い食べ物」です。

例えば、かぼちゃ、さつまいも、トウモロコシ、にんじん、じゃがいも、お米、大豆製品、りんご、キャベツ、インゲン豆など。
さらに胃腸を弱らせる原因になるのが「湿(体の余分な汚れや水分や汚れ)」、「ストレス」と言われます。
「湿をとる食べ物」は紫蘇、もやし、春雨、冬瓜、そら豆、昆布、大豆製品、小豆、はと麦、緑茶、コーヒー、とうもろこしのひげ茶など。

次に「気(ストレス)を巡らせる食べ物」は、金柑やグレープフルーツなどの柑橘系、パクチー、セロリ、ミント、パセリ、春菊、ハーブティーなど香りのよい物です。

これらも合わせて摂ると脾も元気になります。
また、肺を補う食養生は「白い色の食べ物」です。

豆腐、レンコン、山芋、梨、白きくらげ、ゆり根、白ごま、松の実、杏仁豆腐、豆乳なども積極的に摂りましょう。
衛気を補う生活養生法
・睡眠を大切に
・肥甘厚味(脂っこい、甘い、味付けの濃い)の食事はできるだけ避ける
・ストレッチやヨガなどで身体をゆるめる
・ウォーキング、ランニングなど有酸素運動で肺を元気に
・冷たい飲食物は控えめに、水も必要以上に摂り過ぎない
・体を冷やさないよう、服装などを意識する
・朝一番の深呼吸
これらを意識して、日々の習慣に取り入れましょう。
乾布摩擦もおすすめ
また、乾布摩擦もおすすめです。乾布摩擦といっても昔のように裸で極寒の中タオルでゴシゴシ…なんてしなくて大丈夫です。

洋服を着たままで構いませんので、鎖骨の端の指一本下にある「中府(ちゅうふ)」というツボから親指の外側にある「少商(しょうしょう)」というツボに向かって摩ってあげてください。
もちろん、温かい部屋で摩ってもらって大丈夫です!
以上をコツコツ続けることで今年は元気に、病気知らずに過ごしましょうね。
2024年9月25日発売 『心と体を整えるおいしい漢方〜季節の食養生で不調を改善』
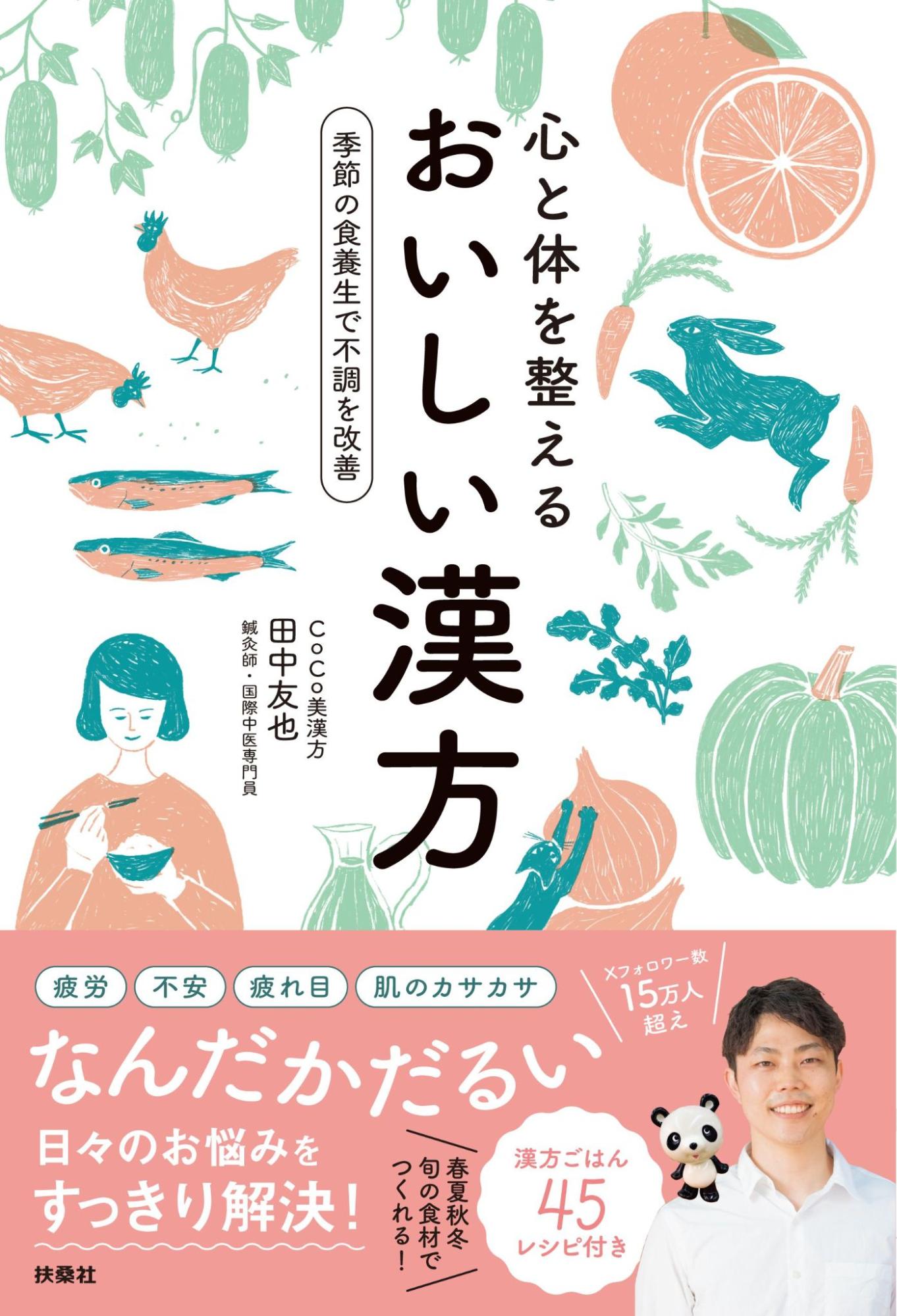
病院に行くほどではないけど、なんか調子が悪い。そんなときは漢方による食養生がおすすめです。
田中友也さんがお勤めの漢方薬局で日々相談にのるなかで習得した、健康改善が期待できる季節ごとの食材や習慣、簡単なレシピまでを、薬膳や漢方的な見地から12か月に分けてわかりやすく教えます。

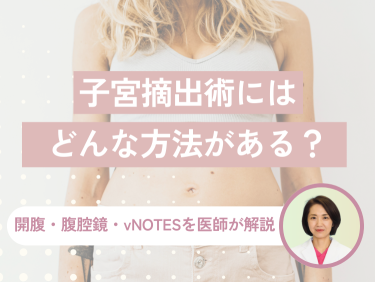
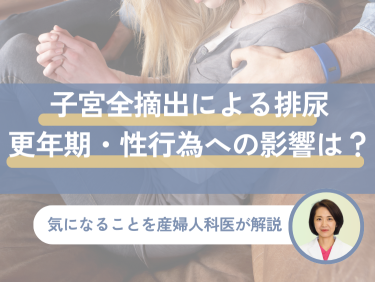
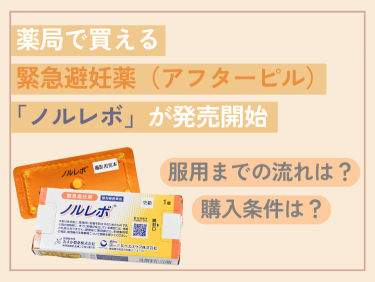



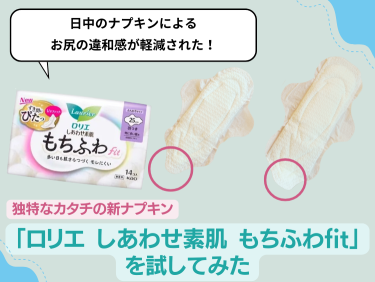



![YES インティメイト・ウォーターローション WB[さっぱり保湿ケア]](/assets/media/2022/02/1721113748052-375x375.jpeg)