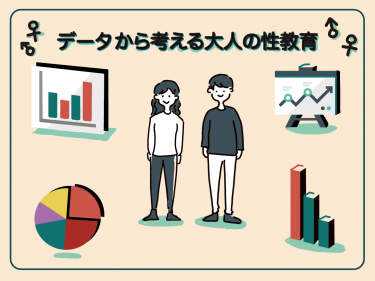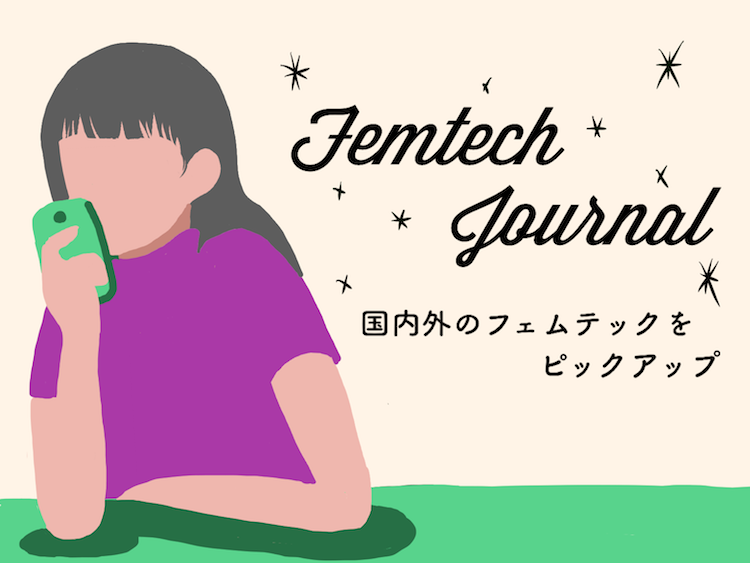
「グリーフケア」という言葉を知っていますか? 大切な人を失った深い悲しみ「グリーフ」に寄り添う、心のケアのことです。
現代では、不妊治療の広がりと共に、その裏側で流産や死産を経験する人も増えています。しかしながら、これらの経験は周りには見えづらいほか、言葉にもしにくいため、悲しみを抱え込んでしまう傾向があります。
「私のせい…」と自分を責めたり、パートナーとどう向き合えばいいか分からなくなったり。その痛みは、決してあなた一人、あるいは女性だけが抱えるものではありません。
だからこそ、その悲しみに寄り添うためのサポート、グリーフケアが必要とされています。
近年、海外では人種や性別、立場に合わせたユニークなサポートや、新しい形のグリーフケアを提供するスタートアップが次々と生まれています。
今回は、海外のユニークな取り組みを紹介しながら、グリーフケアのありかたや、もし悲しみを抱え込んでしまいそうになった際のサポートを見つけるためのヒントをお届けします。
「グリーフケア」とは?—悲しみを無理に消さない、という選択

もし深い悲しみに暮れたとき、私たちは「早く元気にならなきゃ」と自分を追い詰めてしまいがちです。
しかし、グリーフケアの考え方は少し違います。悲しみは「克服する」ものではなく、自分のペースで向き合っていくもの。そのプロセスに寄り添うのが、基本的な考え方です 。
グリーフケアとは、死別などによって深い悲しみ(グリーフ)を抱えている人に寄り添い、その人が回復していくプロセスを支援する取り組みのことです 。
最も重要な原則は、悲しみの感情やそれに伴う行動を否定せず、ありのままに受け入れること 。
専門家や家族、友人が、ただ静かに話に耳を傾けることで、孤立感を和らげ、自分の感情を肯定できるよう手助けをします 。
深い悲しみは、心だけでなく身体にも、疲労や不眠といった様々な影響を及ぼします 。グリーフケアは、こうした心身の不調を管理し、バランスを取り戻す手助けともなります 。
流産、死産。その痛みの正体とは?

流産や死産の悲しみには、他の別れとは違う、特有の痛みがあります。その背景にある、社会的なこと、心のこと、そして体のことを知るのは、自分を責める気持ちを和らげ、その痛みが正当なものであると受け入れるための第一歩になります。
社会から見過ごされる悲しみ「公認されない悲嘆」
流産や死産による悲しみは、専門用語で「公認されない悲嘆(disenfranchised grief)」と呼ばれることがあります 。これは、その喪失が社会的に重要と認められず、公に悲しむ機会やサポートを得にくい悲嘆のことをいいます 。
多くの死別にはお葬式のような社会的な儀式がありますが 、流産や死産の場合、特に妊娠初期ではそうした場がほとんどありません。そのため、周囲の人々はその喪失の重さを理解しにくく、「次があるよ」といった悪気のない言葉で、かえって当事者を傷つけてしまうことがあります 。
「私のせい?」—終わらない自責の念と、二人の悲しみ
流産や死産を経験した女性の多くが、激しい罪悪感や自責の念に苦しみます 。理屈は母親だけに原因がないとわかっていても、その死が自分自身の胎内で起きたという事実が、怒りや無念の矛先を自分自身へと向かわせてしまうのです 。
そして、この悲しみは決して女性一人のものではありません。パートナーもまた、親になるという夢を失い、深い悲しみを抱えています。
しかし、男性は「強くあらねば」「パートナーを支えなければ」というプレッシャーから、自分の感情を内に秘めてしまいがちです。
その結果、女性側から見ると「悲しんでいないように見える」という温度差が生まれ、すれ違いや孤独感につながることがあります 。この経験は、カップルにとって共通の喪失であり、二人で向き合うことが非常に重要になります 。
世界に広がる多様なサポートの形
世界では、グリーフケアの形が多様に進化しています。みんなが「同じサポート」を受けるのではなく、人種や性別、その人の立場に合わせた、よりパーソナルなケアが生まれています。
特にイギリスでは、NHS(国民保健サービス)流産・死産後のカウンセリングや専門の助産師による継続的ケアが提供される取り組みが広がり、グリーフケアについてオープンに語られています。
またアメリカは州によってバラつきはありますが、LGBTQ+カップルが子どもを持つことも社会的に認知が広がっているので、異性カップル同様にサポートが必要であるという意識も浸透しつつあります。
LGBTQ+ファミリーの悲しみをケアするコミュニティ
Return to Zero: H.O.P.E. (RTZ HOPE)(アメリカ)
LGBTQ+の親が直面する特有の課題を認識し、コミュニティに特化したサポートグループやワークショップを提供しています。家族計画における複雑な道のりや、親の悲しみが軽視されがちな状況にも焦点を当てています 。

人種と向き合うケア、黒人女性のためのコミュニティ
イギリスにおいて黒人女性の周産期死亡率が他の人種より著しく高いという現実に立ち向かうために設立されました。医療における人種間の不平等をなくすための政策提言と、当事者である黒人女性への直接的なサポート(グリーフケアを含む)を両輪として活動しています。
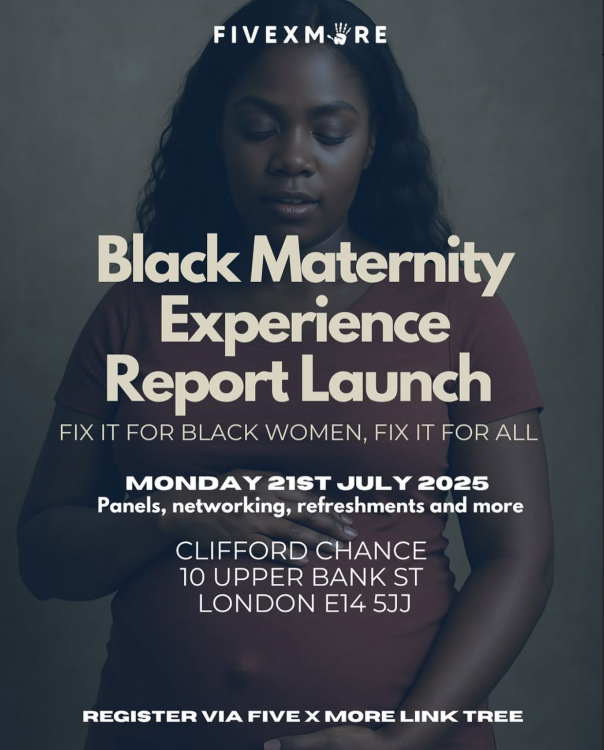
遺族としての父親に寄り添い企業向けトレーニングも行う
多くの男性は、自分の悲しみはパートナーのそれに比べて二の次であり、自分の感情を表現すること躊躇し、自分の悲しみを抑圧し、パートナーをサポートすることに徹することで、無力感を乗り越えようとする傾向があるそうです。
また、男性は自身の身体で起きたことではないため、その喪失を語る言葉を持っておらず悲しみを溜め込んでしまうことも問題視されています。
英国Podcast Awardsの受賞歴もある、2人の父親が運営するポッドキャストでは、赤ちゃんを亡くした後の父親の悲嘆について、あらゆるトピックを扱っています。同じ経験をした父親たちに、実践的でアクセスしやすいサポートを提供することを目的としています 。

赤ちゃんをケアする立場の人々へ:保育士や里親のグリーフケア
悲しみの波紋は、親や家族だけに留まりません。保育士や里親など、仕事として赤ちゃんのケアをしていた人が、その子の死を経験することもあります。この団体は、そうした極めて特殊で困難な状況に置かれた人々を支援するという、他では少ない重要な活動を行っています。

日本国内で利用できるサポートと窓口
日本国内にも、悲しみに寄り添うためのサポートの輪が広がっています。同じ経験を持つ人々と語り合う「ピアサポートグループ」、専門家による「カウンセリング」、そして地方自治体が提供する「公的な相談窓口」などがあります。
日本の主要なグリーフケア団体・相談窓口
【ピアサポート・NPO法人】
流産・死産、新生児死などを経験した家族のための相互支援団体。オンラインコミュニティや全国各地での「ポコズカフェ」と呼ばれるお話会を運営。
主にSIDS(乳幼児突然死症候群)で子どもを亡くした家族を支援するが、流産・死産経験者も対象。全国に地区会があり、ミーティングを開催。
働く天使ママコミュニティ iKizuku (オンライン / 関東)
流産・死産などを経験した「働く女性」のためのピアサポートグループ。職場復帰やキャリアに関する情報提供やオンラインお話会を実施。
https://i-kizuku.amebaownd.com
当事者へのカウンセラー派遣や、支援者を育成する研修を実施。医療関係者向けのプログラムも提供。
https://perinatalloss-support.com
NPO法人ペリネイタル・ロスサポートなごみ(全国 / オンライン)
流産・死産した方をサポートしたい人に向けた研修や、当事者のお話会やコミュニティづくり、医療機関への小さな産着の寄付、啓発活動など幅広く活動。
【地方自治体・公的機関の窓口】
お住まいの市区町村の保健センターなど
各自治体の保健福祉センターやこども家庭センターには、保健師や助産師が常駐しており、心身の不調について相談できます。「母子健康包括支援センター」などの名称で設置されています。
専門の研修を受けたピアカウンセラーや医師が、流産や死産を繰り返す方の悩み相談に応じ、情報提供を行っています。男性もご相談できます。
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/sodan/h_soudan
自分とパートナーをケアするためにできること

流産や死産という経験は、当事者だけでなく、その周りの人々にとっても大きな出来事です。ここでは、悲しみを経験した本人、そしてその人を支えたいと願う家族や友人が、共に心のケアをしていくためにできることをまとめました。
当事者の方へ
どんな感情も、自然で正当なものです。悲しいときは泣き、何もする気が起きないときは休み、自分にそう許可してあげることが、ケアの第一歩です 。
気持ちをノートに書き出したり、パートナーと気持ちを共有したりすることも助けになります 。
心の痛みは、身体のエネルギーを大きく消耗させます。栄養のある食事や十分な睡眠を心がけ、無理のない範囲で散歩などの軽い運動を取り入れると、心身のバランスが整いやすくなります 。
支える方へ
「早く元気になって」といった励ましよりも、「辛かったね」と気持ちに寄り添うことが大切です 。相手の感情を否定せず、ただ話を聞く安全な場所を提供しましょう 。本人が話したくないときは、無理に聞き出さない配慮も必要です 。
家事を手伝ったり、食事を用意したりといった具体的なサポートは、当事者が心身を休めるための大きな助けになります 。相手の負担を少しでも軽くすることを考えてみましょう。
二人で悲しみと向き合う
流産や死産は、カップルにとって共通の悲しみです。しかし、悲しみの感じ方や表現方法は人それぞれ。
お互いの気持ちを正直に伝え合い、「自分も悲しい」と共有することで、孤独ではなく、二人で経験に向き合うことができます 。
今は「次のこと」を考えるのではなく、まずはお互いをいたわる時間を大切にしましょう 。
専門家やサポートを頼る
日常生活に支障が出るほどの辛さが続く場合は、専門家を頼ることをためらわないでください。それは弱さではなく、自分や大切な人を守るための賢明な選択です 。
産婦人科や心療内科、カウンセラーは、専門的な立場から心と体の回復を支えてくれます 。
それぞれのペースで未来へ

流産や死産という経験は、当事者だけでなく、その周りの人々の人生にも深い跡を残します。しかし、その悲しみの中に、ひとりきりでいる必要はありません。
その深い痛みは「グリーフ」とよばれる、自然な感情です。そして、その痛みに寄り添う「グリーフケア」という考え方と、具体的なサポートが存在します。
世界では、人種や性別、立場に応じた多様なケアが生まれ、日本でも、支えのネットワークが育っています。
癒やしとは、悲しみを忘れることではありません。
赤ちゃんが生きていたという事実、親になったという記憶、そしてその喪失の悲しみを、人生の一部として大切に抱きしめながら、未来へと歩んでいくことです 。




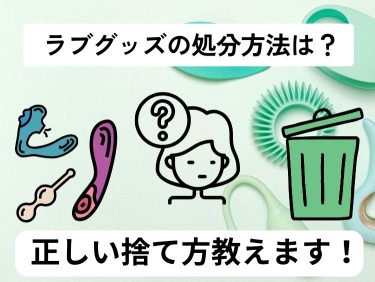


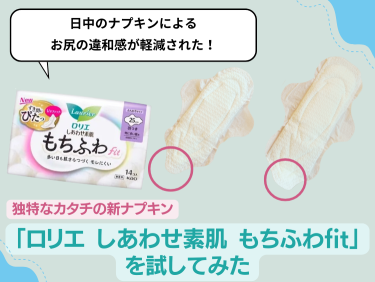



![YES インティメイト・ウォーターローション WB[さっぱり保湿ケア]](/assets/media/2022/02/1721113748052-375x375.jpeg)