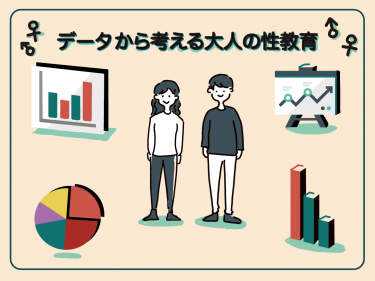ここ数年「ありのままの自分を愛そう」というボディ・ポジティブなメッセージがメディアや著名人の発信で増えてきています。
その一方で、美容整形市場は右肩上りで成長を続けています。
「外見の良さ」は、自分自身の価値や人生の充足感と直結したものとしてとらえられ、現代人は広告やソーシャルメディアで「ダイエット」の情報に接して生活することが当たり前となっています。
このような社会環境で問題視されている「摂食障害」は、女性が9割を占める疾患といわれています。
摂食障害は大きく分けると極端な食事制限を行い低体重を維持しようとする拒食症(神経性食欲不振症)と、むちゃ喰いなどを繰り返す過食症(神経性過食症)のふたつがあります。
さらに、近年では、DSM-5(米国の診断基準)に過食性障害と回避制限性食物摂取症という新たな分類も加えられています。
また、世界的に子どもたちの摂食障害が増加傾向にあり、子どもや青少年の20%に摂食障害の兆候が見られるという調査結果が出ており、社会全体で解決すべき問題として認知が広がっています。
摂食障害を解決しようとするサービス

摂食障害を引き起こす要因を解明する研究が進んでいますが、はっきりしたことはわかっていません。要因としては、生物学的・心理的・社会文化的なものがあり、それらが相互関係を起こしていると考えられています。
摂食障害は、心身に大きなダメージを与えるため、治療を行うことが重要です。
女性の身体に与える影響の中で特徴的なものとして、拒食症による生理不順や、体重減少性無月経があります。
さらに急激な減量で女性ホルモンに影響を与え、若年性骨粗鬆症など骨の健康に関わる問題も生じます。
また、女性特有の課題として、摂食障害が母から娘へと受け継がれていく場合があることもソーシャルメディアで言及されるようになってきました。
摂食障害の治療は、症状や症状の重症度によって異なりますが、長期で取り組む場合が多いため、コロナ禍以降に浸透したオンライン診察サービスと相性が良く、多様なサービスが生まれています。
そして治療だけではなく、人々のボディイメージ形成に大きな影響を与えるソーシャルメディアプラットフォームも有害な情報発信を防ぐ取り組みが少しずつ広がっています。
ドイツの医療政策「DiGA」承認のSelfapy
ドイツのSelfapyは、科学的根拠に基づいた認知行動療法で、過食症やうつ病などを12週間のコースで治療するサービスを提供しています。
このサービスは、ユーザーの5人に1人以上が、コース終了後も症状を再発しなかったり、寛解といわれる最小限の状態に抑えられる効果などが認められ、ドイツ政府が推進するデジタルヘルスプログラムの「DiGA」の認定を受けています。
認定を受けたサービスは使用料金が公的医療保険で払い戻しされるので、利用者の金銭的負担が抑えられます。
摂食障害の当事者が立ち上げたEquip
10代の頃に拒食症だった経験のあるクリスティーナ・サフラン氏らが立ち上げたEquipは、オンラインの治療プログラムを提供しています。
サフラン氏は自身の摂食障害の治療過程で、医師、栄養士、セラピストの予定を個別に調整したり、高額なヨガなどの自然派治療プログラムに頼ったりしていました。その経験から、治療を受ける労力と金銭的なハードルの高さを実感し、現在の摂食障害治療は患者に寄り添ったものではないことに問題意識を抱きました。
Equipでは、専門家による治療を提供していますが、家族療法(Family Based Treatment)といわれる方法を採用しており、専門家だけではなく家族が摂食障害を理解し解決に向けて協力することを促しています。
マイノリティの人々の摂食障害ケアを提供するArise
Ariseは、摂食障害の経験があるアマンダ・ダンブラ氏とジョアン・チャン氏によって立ち上げられました。
摂食障害について、単なる食事や身体だけの問題ではなく、摂食障害を生み出す文化を理解してケアしていくことを重視しています。
そして、BIPOC(黒人、先住民、有色人種)の人々や、LGBTQ+の人々は摂食行動の乱れがあっても、白人の人々に比べて治療を受ける割合が低いという課題があります。
そのため、Ariseにはケアを行う専門家に有色人種やクィアの人々が在籍し、患者のさまざまな文化背景を理解して治療を行える環境を用意しています。
YouTubeの取り組み
2023年4月、YouTubeは、摂食障害に関するコンテンツ・ポリシーを更新しました。
参考: 摂食障害に関するコンテンツの方針の見直し(YouTube Japan Blog)
YouTubeで発信されるボディ・イメージにまつわるコンテンツに摂食障害を美化したり、助長する内容が増えてきたため、プラットフォーム側で規制をすることを取り決めました。
さらに影響を受けやすい若年層に対して年齢制限をしたり、「精神的危機に関する情報パネル」の表示を行なっています。
Instagramの取り組み
世界最大の画像共有プラットフォームであるInstagramは、ソーシャルメディア上で「完璧な身体」というボディ・イメージを植え付ける価値観のもととならないよう、詳細なコンテンツポリシーを設け、ボディ・ポジティブを発信するインフルエンサーとコラボをしています。
参考:摂食障害やネガティブなボディイメージに悩む人々をサポート(Instagramブログ)
さらに、摂食障害やネガティブな身体イメージに悩んでいる人へのアドバイスとともに、友達のInstagramの投稿に摂食障害を暗示する内容があった場合にすべきこと・すべきでないことを明示しています。
すべきこと:
友達に今の気持ちを尋ねてみる。例えば、「最近調子はどう?何か話したいことがあったらいつでも話を聞くよ」などと尋ねます。「私」がどう思っているかを伝える。例えば、「朝食も昼食も食べなかったから、ちょっと心配で」などと言います。友達が話したくない、または心配してもらうことは何もないという姿勢を見せた場合は、私でよければいつでも話を聞くよ、ということを伝える。話をしたり、映画を見るなどして友達と一緒に時間を過ごし、大切に思っていることを示す。自分の生活がお手本になるようにする。また、自分や他の人の外見について否定的なコメントをしないようにします。友達が調子が良くないと言った場合は、カウンセラー、医師、栄養士や他の医療専門家に相談することを考えているか尋ねる。例えば、「助けになるかどうかわからないけど、このことを医師に相談することは考えているの?」と聞いてみましょう。摂食障害のリスクを理解するのに役立つ、無料で匿名のオンライン診断を受けてみるよう提案することもできます。すべきでないこと:
「あなたは自分を大事にしていない」など、相手個人を批判するような言葉を使う。相手の外見や行動に対して、恥や罪の意識を感じさせたり、非難する。「ダイエットをやめればすべて解決する」など、単純な解決策を提示する。治療するよう求める。肥満症の治療薬登場の影響
アメリカ合衆国保健福祉省によると、近年のアメリカの肥満率は41.9%といわれています。
日本の肥満率が男性 33.0%、女性 22.3%であることと比べると、アメリカが高い割合であることがわかります。
そんなアメリカの国民病ともいえる肥満に関して、治療薬が現れたことが話題になっています。
元々は糖尿病治療のために開発されたセマグルチドといわれる治療薬が、2021年に肥満症治療薬としてFDAに承認され、イーロン・マスクなどの有名人が使用していることを公表し、メディアでも「待望のやせ薬」の登場として取り上げられています。
オンライン診察を行うスタートアップのRoは、男性のEDや脱毛症などの「メンテック」といわれる領域で有名な企業ですが、2023年3月以降に「減量事業」として、肥満症治療薬(WegovyとOzempic)の提供を開始しました。
Roは、新事業のキャンペーンとしてニューヨーク市の100以上の地下鉄駅に合計1,000以上の広告を掲載しました。
しかし、薬の副作用を軽視している点と、太っていることは治療すべきことという印象を植え付けようとしている点について、批判されています。
痩せるために薬を自己注射している人の写真やキャッチコピーが駅の壁面、柱、階段の段差にまで埋め尽くす様子は異様な雰囲気です。
肥満症治療薬は、治療を必要とする「肥満症」の人(※1)にとってはイノベーションといえるものですが、ネットで購入可能であったり、個人輸入可能であることから、「肥満」ではない人々が美容やダイエット目的で使用することが警戒されています。
アメリカの大手メディア『TIME』は、肥満症治療薬がメディアで話題になること自体が摂食障害の人々にとって症状を起こすトリガーになったりする有害な情報になり得るため、減量を美化する情報発信の問題点を指摘しています。
しかし、デジタルヘルスのスタートアップの数々がRo同様に肥満症治療薬のオンライン処方に乗り出そうとしています。
メンテックとフェムテックで有名なHims & Hersも減量事業に向けての準備を進めています。
※1 : 「肥満(BMIが25以上)で、肥満による11種の健康障害(合併症)が1つ以上あるか、健康障害を起こしやすい内臓脂肪蓄積がある場合に診断され、減量による医学的治療の対象になります。」一般社団法人日本肥満学会サイトより
http://www.jasso.or.jp/contents/wod/index.html
社会で解決する姿勢の重要性
私たちは現在、偏ったダイエット重視の食文化や、過度に美化されたボディ・イメージに晒されています。
摂食障害は女性に多い病気ですが、年齢や性別問わず誰でもなり得るものです。
近年は若い男性やLGBTQ+の人々の摂食障害を見過ごしてはいけないという意見も上がっています。
全米摂食障害協会 (NEDA) では、ソーシャルメディアによって自身のボディ・イメージを良くない方向に捉えないためのセルフケアとして、以下のヒントを提示しています。
- フォローするアカウントや閲覧するメディアを選んでください。自尊心に悪影響を与えたり、あなたの価値観と合わないものから距離を置いてください。
- スクリーンタイム(閲覧時間)を制限しましょう。ソーシャルメディアに触れる時間が長いほどネガティブな情報に接する機会も増えます。
- ソーシャルメディアを見ていて感じた「違和感」を大事にしてください。ボディ・イメージについて独断的な意見を押し付けてくるものを批判的思考で見て、押し付けに屈しないようにしましょう。
ご自身や周りの人の健康が心配な場合は、摂食障害全国支援センターの相談ほっとラインにご連絡ください。

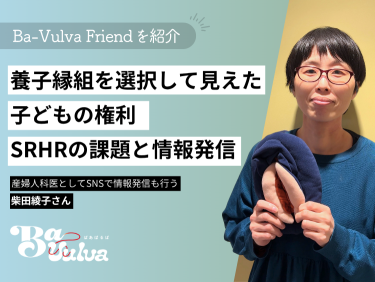

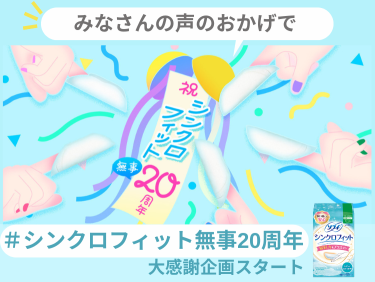

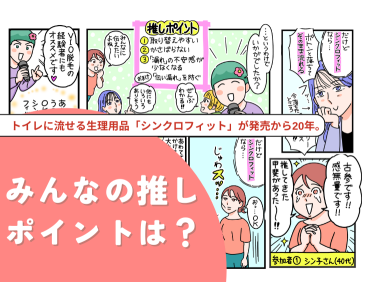

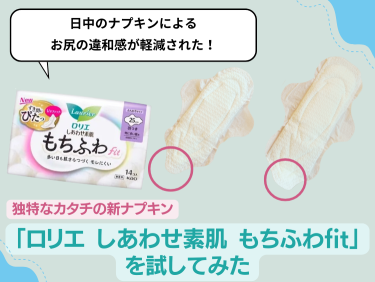



![YES インティメイト・ウォーターローション WB[さっぱり保湿ケア]](/assets/media/2022/02/1721113748052-375x375.jpeg)