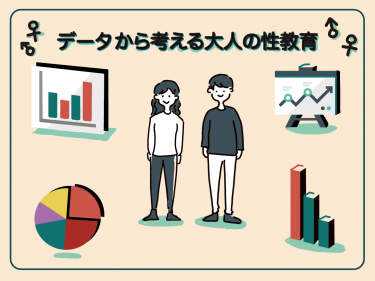Ba-Vulva(ばあばるば)は、外陰部の構造を楽しく正しく理解し対話するためのパペットです。セックスカウンセリングやクリニック等で、専門家の方々にクライアントと対話するツールとしても使ってもらいたいと思っています。
情報を知るだけでなく、対話をすることで、大切な人たちと健やかな日々を過ごしてほしいという想いがあり、セクシュアルウェルネス、ウェルビーイングな社会に寄与したいと思っています。
ばあばるばでは、<Ba-Vulva Friend>と題して、国内外で国内外のセクソロジストや性教育関係者など、セクシュアルウェルネス業界で活動する方々にインタビューをしてます。
今回は、タイで臨床心理士、セックスカウンセラー(sex therapist*)として活動しているNestさんにお話を伺いました。
タイのセクシュアルウェルネス事情やセクソロジーについて学ぶことになった経緯について聞きました。
*sex therapist=相談だけでなく心理療法・治療を行う専門家

MISA: Nestさんはタイでカウンセラーをされています。性科学を学ぼうとしたきっかけを教えてください。
NEST: 私はタイ出身で、アメリカで臨床心理学の修士号を取得したあと、タイで6、7年働いていました。その後、オーストラリアのカーティン大学でセクソロジー(性科学)の修士課程を修了しました。
私は主に心理療法の分野を学んできていたので、性科学はまだ新しい分野です。
心理療法をする中で、クライアントや子どもたちの精神的な問題がセクシュアルヘルスと関連していることもあり、オーストラリアで性科学を学ぼうと思いました。
日本と同様、タイでも性に関する話題はまだタブー視されることが多いです。そして、タイと日本にはいくつかの共通点があると思っています。
正確か分かりませんが、極端な二つの視点が存在していると感じます。ひとつはとても閉ざされたもので、もうひとつは逆にとてもオープンなものです。その中間があまり存在しないように感じます。
年配の世代に多いですが、若い世代でも厳格で保守的な家庭や学校で育った人たちは、性に関する話題を極端に避けがちです。
一方で、まったく逆の立場の人たちもいます。性に関する話題を積極的に話す人たち、西洋文化を取り入れて、セクシュアルヘルスや会話を前向きに捉える人たちです。
MISA: そうなんですね。確かに、タイはLBGTQなどセクシュアリティについて、とても理解が進んでいる印象があります。
Nest: そうですね、タイはLGBTQコミュニティの中心地のような存在になりつつあり、多くの人々が集まります。私は、そのことを誇りに思っています。
LGBTQのプライドを推進し、世界でもトップレベルのトランスジェンダーや性別適合手術が行われています。しかし同時に、非常に閉鎖的な人々は、性に関してもっとオープンになりたいと願う人々を批判することもあります。
これは深い話ですが、タイで心理療法士として働いてきた中で感じた一部のことです。そのため、セクシュアルヘルスについて話すことに恥ずかしさを感じてセラピーに来る人もいます。性に関する話題がまだタブー視されているからです。
家族を語るとき、性の健康の問題は無視できない
MISA: 今後はセックスセラピストとして活動されるのですか?
NEST: 将来的にはそう自称できるようになりたいですね。セックスセラピストとしての道はまだ始まったばかりです。現在学んでいるコースを修了した後、一般的なメンタルヘルスの問題と、性的な問題の両方に対してセラピーを提供できるようにしたいです。
セックスセラピストになりたいと思ったきっかけは、家族療法やカップルセラピーをしたいという思いと密接に関わっています。
MISA: というと?
NEST: 私が最初に目指したのは、カップルセラピストや家族セラピスト(家族のコミュニケーションや関係性の問題解決を図るセラピスト)になることです。でも、家族やカップルについて考えるとき、彼らのセクシュアルへルスやセクシュアリティを無視することはできないですよね。
この二つは密接に関連していて、家族セラピーやカップルセラピーを学ぶ中で、セクシュアルへルスやセクシュアリティについても学び、セックスセラピーを行えるようになりたいと思いました。
MISA: カウンセラーとして働いている中で、具体的にはどのようなセクシュアルヘルスにまつわる相談がありましたか?
NEST: 思い出せるケースのいくつかは、性的トラウマや性的虐待に関するものです。幼少期や過去の恋愛関係で性的虐待を受けた経験があり、その影響でセラピーに来る方がいます。
時には、直接的なセクシュアルヘルスの問題を抱えてセラピーに来ることもあります。例えば、現在のパートナーがとても理解があり、優しく接してくれても、性行為に対して恐怖を感じ、うまくいかないというケースです。
もう一つのケースは、より間接的な影響によるものです。現在の性的関係に問題はなくても、過去に受けた性的虐待が原因で、自信や自尊心、自己コントロール感に影響を与えたり、精神的な健康に悪影響を及ぼしたりすることがあります。
二番目によく見られる問題は、自分自身の行動を異常だと感じるケースです。
例えば、自分の性的欲求が強すぎる、自慰行為の回数が多すぎると不安を感じたりします。「こんなことを考えている私はおかしいのか?」「こんな欲求を持つ自分は変なのか?」と自分に問いかけることがあります。
時には、「性的逸脱障害(普段のその人がしないような性的な行為や言動をする状態)」と呼ばれるものが実際に存在し治療が必要なケースもありますが、性的な行動が正常範囲内であるにもかかわらず、それを過剰だと感じたり異常だと思ったりすることも多いです。
MISA: どのように対処されているのですか?
Nest: その行動が実際には健康的であることを理解してもらう一方で、なぜそれを異常だと感じてしまうのかを探るサポートを行います。
クライアントは、自分の行動に対して不安や疑問を抱き、「なぜ私はこう感じるのだろう?」と悩むことがよくあります。
私が性科学を学ぶ前は、異なるアプローチとして、心理療法でよく使われる認知行動療法(CBT)を行っていました。
CBTは、クライアントの思考パターンを理解することを重視します。その思考を理解することで、なぜ特定の行動をとるのかが分かるようになります。
例えば、自信のなさを補うために性的な行動をとっている場合があります。他にも、孤独感や他者とつながりたいという欲求が原因であることもあります。
CBTでは、その行動の背後にある問題を見つけ出し、根本的な原因にアプローチします。そのため、行動をやめるだけではなく、なぜその行動をとっているのかを深く掘り下げる必要があります。
MISA: CBTでは、質問を繰り返すことでクライアントの根本的な原因を探していくんですね。
NEST: はい、質問を重ねて、時には図を描いて視覚的に理解を深めることもあります。
特に繰り返される行動の場合は、円を描くことで、その行動がなぜループしているのかが見えてくることがあります。
どこか一つの行動を止めることで、そのサイクル全体を止めることができるかもしれません。
また、彼らには自分の体験を整理してくれる人がいないことも多いです。そのため、私たちはある意味で鏡のような役割を果たします。
「これがあなたが私に伝えていることです」と反射させて、整理し、それを彼らに返します。セラピーは時に、クライアント自身を映し出す鏡のような存在になり得ます。
思考から体へ。体の感覚にも焦点を当てるカウンセリングを
MISA: とても興味深いですね。他に使われているアプローチがあれば教えていただけますか?
NEST: タイに来てから学んだことの一つは、体の感覚や行動面にもっと焦点を当てることです。以前は、CBTの主な焦点である思考過程に重点を置いていました。つまり、「何を考えているのか」「なぜそうするのか」を探るというものです。
こちらに来てから学んだのは、思考だけでなく、生理的な反応や体の感覚、例えばにおいや感覚、景色といったものも、セクシュアルヘルスの改善に影響を与えるということです。
欲望を高めたい人の場合、自分の体をもっと探る必要があるかもしれません。それは単に体だけでなく、どんなにおいや風景が自分にとって心地よいのか、ということも含まれます。
逆に、性的欲求が非常に高い人の場合は、体や周囲の環境を探ることで、欲求を抑える助けになるかもしれません。つまり、両方の方向に働くことがあります。
特定の性的興味を持っている人の場合、それが他の人に問題を引き起こさない限り、そして本人がそれを楽しんでいる限り、それは問題ないということを学びました。
最終的に、本人が幸せで、他に問題を引き起こさないのであれば、最後に取り組むべきことは、セクシャルポジティブな考え方かもしれません。
「それでいいんだよ。あなたの興味は自然なもので、受け入れられるものだよ」と肯定できる考え方です。
ーー
後編では、タイのセクシュアルヘルスの状況、そして、身体の構造を理解することの大切さについてお聞きしました。こちらからご覧ください。
ーー

Ba-Vulva(ばあばるば)は、おばあちゃんたちと手作りで作っています。ばあばるばに込めた想いやプロダクト詳細はこちらをご確認ください。
https://laundrybox.co.jp/BA-VULVA_jp
本記事はランドリーボックスが制作している性教育パペット「Ba-Vulva(ばあばるば)」の公式サイトの記事を一部編集の上、転載しています。





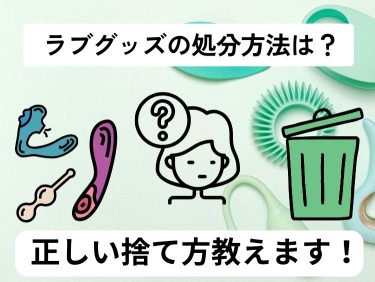


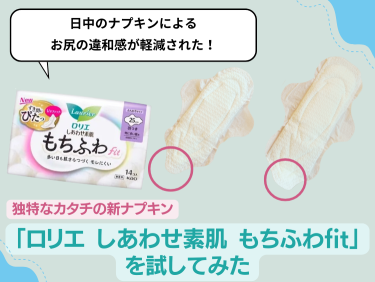



![YES インティメイト・ウォーターローション WB[さっぱり保湿ケア]](/assets/media/2022/02/1721113748052-375x375.jpeg)